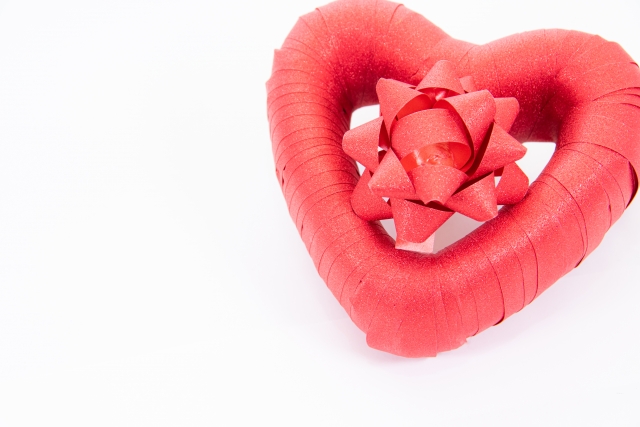不整脈の種類の違いと症状の特徴

「不整脈」とは心臓の脈拍が正常とは異なるタイミングで起きるようになった状態を指します。
不整脈には、脈が速くなる頻脈性不整脈、脈が遅くなる徐脈性不整脈、そして予期しないタイミングで脈が生じる期外収縮などがあります。
ここでは不整脈はどんな病気なのか、その具体的な種類や症状などに関して詳しく解説します。
不整脈の種類

心臓は右心房、右心室、左心房、左心室の4つの部屋に分かれており、右心房にある洞結節が電気信号を発生させ、この電気信号は、右心房から左心房、両心室へと順次伝わることになります。
心臓は通常であれば心筋細胞における電気信号を規則正しく伝達して正常に動いています。
この電気信号の流れが乱れる、あるいは遅くなったり、速くなったりしている状態が「不整脈」です。
症状の程度は不整脈の種類によって異なり、少し脈が飛ぶ程度のものがある一方で、突然死を起こす非常に怖い不整脈もあります。
例えば、スポーツ選手は通常よりも心拍数が遅くなることがありますが、これは病的なものではありません。
一方で、危険な不整脈になると、脳への血流が不十分となり、失神やふらつきを起こすことがありますし、不整脈により心臓が血液を全身に十分に供給できなくなれば息切れや呼吸困難などの心不全症状を呈することもあります。
不整脈の中でも頻度的にもっとも多いのは、予定されていないタイミングで脈が生じる期外収縮と呼ばれる不整脈です。例えば3回に1つというように、時々脈が飛ぶことを自覚する場合には期外収縮の可能性を検討する必要があります。このタイプは通常では危険性のない不整脈であり、発生しても自覚症状が現れないことがあります。
不整脈は脈が速くなる頻脈性不整脈と脈が遅くなる徐脈性不整脈に分類されてます。一般的には脈拍数が1分間あたりに50以下の場合を徐脈性不整脈、100以上の場合には頻脈性不整脈と呼びます。頻脈性不整脈と徐脈性不整脈はそれぞれさらに細かく分けられています。
ここからは、いくつかの不整脈を取り上げ、さらに詳しく見ていきましょう。
心房細動とは

心房細動という不整脈は、本来は一定リズムの電気活動で動いている心房の部屋が、無秩序に痙攣している状態を呈するため、正常の規則的な脈ではなく、不規則な脈のリズムになってしまいます。心房細動には動悸やめまいなどの症状が認められます。
近年では高齢者を中心に知らないうちに心房細動を罹患している方が増えており、この不整脈を患うと心臓の中に血液の塊ができやすくなります。
心房細動では心房内に血栓を形成し、その心房内の血栓は血流に乗って全身へ飛ばされる恐れがあるため、脳梗塞の発症リスクも上昇すると考えられています。
心臓の中にできた血液の塊が遊離して脳の動脈の方に流れていき、脳の血管が詰まって閉塞してしまうことが原因で起こる脳梗塞のことを心原性脳塞栓症と呼んでいます。
動悸などの症状が出現した際には、心房細動などの不整脈がないかどうか医療機関で詳しく調べてもらった方がよいでしょう。
発作性上室頻拍とは
発作性上室性頻拍は、発作的に脈が速くなる頻脈性不整脈のひとつです。
基本的には、心臓は洞結節と呼ばれる場所から規則正しく心臓のそれぞれの部屋を動かすように電気信号が発生し、心臓全体に伝わっています。しかし、余分な電気経路が形成されると、そこを伝って心臓が早く動いて脈が早くなるのです。
発作性上室性頻拍は心臓に余分な電気経路が生じる、あるいは生まれつき必要以上の電動経路が存在することで引き起こされます。頻拍発作が起こる機序の違いから房室結節回帰性頻拍、WPW症候群、心房頻拍という3つの種類に大別されています。
この不整脈では、通常よりも脈が速くなるために動悸症状を感じるのみならず、頻脈に陥るために心臓から全身へと血液を十分に送り出せずにふらつきやめまい症状を呈し、ひどい場合には失神することもあることが知られています。
洞機能不全症候群とは

洞機能不全症候群は脈が遅くなる徐脈性不整脈の一種で、心臓の脈の速さを支配している場所である洞結節部位の電動機能が悪くなるために引き起こされる脈拍異常を指しています。
主たる症状としてはめまいや失神を起こすことが知られており、また無症状の方でも偶然に健康診断などの機会に脈が遅いことを指摘されて、本疾患と診断されることがあります。
この不整脈では、脈が遅くなるタイプによって3つの群に分類されます。
まず、I群の洞性徐脈は、通常1分間あたりの脈拍数が50回以下の状態が慢性的に続く状態をさします。
次に、II群の洞停止では、正常な脈が時に完全に停止してしまう状態になります。
そして、Ⅲ群の徐脈頻脈症候群は脈拍リズムが急激に速くなったり遅くなったりする、あるいは正常化するときに数秒停止する状態が認められます。
房室ブロックとは

房室ブロックは心臓の電気活動が阻害されている徐脈性不整脈のひとつで、心房と心室間の電気信号を介した情報伝達が正常に機能していない状態を指します。
房室ブロックは重症度に応じてI度からIII度まで分類され、全く症状を認めることなく治療介入の必要がないタイプもあれば、めまいや失神を呈して治療を要する種類もあります。
例えば、I度房室ブロックでは、心房から心室への電気伝導が健常時よりも遅くなりますが、実際の心室の心拍数は減少しません。II度以上になると心拍数が遅くなって脈が飛ぶことがあり、息切れやめまいなどの症状を自覚することもあります。
房室ブロックは重症度が上がるにつれて心拍が遅くなり、最悪の場合には心停止に繋がってしまうことも懸念されます。
WPW症候群とは

生まれつき正常な刺激伝導系である房室結節以外に心房と心室の間をつなぐ余計な伝導路が存在する病気があり、その病気のことをWPW(ウォルフ-パーキンソン-ホワイト)症候群といいます。
WPW症候群の発症頻度は1000人に数人と言われています。
この余計な伝導路のことを副伝導路と呼び、副伝導路があることが心電図ですぐにわかる患者例を顕在性WPW症候群といいます。
心電図の所見としては、副伝導路を通じて心室が興奮する際に生じるデルタ波が特徴的です。
WPW症候群は、心房と心室の間に電気刺激を伝える余分な伝導路(副伝導路)が生まれつきあることで発生する病気であり、心拍数が異常に速くなる頻脈がみられることが時にあります。
WPW症候群では、症状がなく、短時間で止まるようであれば、積極的な治療は必ずしも必要ではありませんが、症状がなくても、頻拍が長時間続くと心不全を引き起こすことがあります。
WPW症候群の症状
大半の患者では動悸(心拍の自覚)が生じ、脱力感や息切れを感じる場合もあります。
WPW症候群の発作は、突然脈拍が速くなり(頻拍)、しばらく続いたあとに突然止まるという症状であり、突然止まる動悸や胸部違和感、不快感として自覚されます。
頻拍により血圧が下がると、ふらつきや目の前が暗くなる感じが出現したり、失神したりすることも時にありますし、頻拍が長時間続くと、心機能が低下して心不全の状態になる場合も想定されます。
注意が必要な心房細動の合併
WPW症候群は発作性上室頻拍の一般的な原因のひとつであり、非常にまれですが、この症候群の人では、心房細動の発生時に心拍数が上昇して生命を脅かす事態になることがあります。
WPW症候群の人では、心房細動の合併が特に危険になる可能性があります。
副伝導路は、電気刺激の正常な伝導路(房室結節を通る経路)よりもはるかに速いペースで電気刺激を伝える結果として、心室の拍動が極めて速くなり、生命に直結することがあります。
心臓の拍動が速くなって、心臓の働きが大きく低下するだけでなく、拍動があまりに速くなると、心室細動という致死的な不整脈へと進行することがあり、直ちに治療しなければ死に至ります。
対策と治療
不整脈に伴う発作のきっかけは、人によって異なります。
体位変換や運動時、あるいは横になる事がきっかけとなる場合には、急激な動作をなるべく避けて、予防する事も出来ます。
発作が出てしまった場合、息をこらえる、あるいは冷たい水で顔を洗ったり、冷たい水を飲むことによって、うまく不整脈が止められる可能性がありますが、改善しない場合は、救急外来などで点滴治療などの対応が必要となります。
また、発作の頻度が多い場合は、薬剤を処方したり、カテーテルアブレーションを行ったります。
カテーテルアブレーションとは、頻拍に関わる組織を焼灼(しょうしゃく)して頻拍を根治させる治療法であり、WPW症候群であれば副伝導路(ケント束)をアブレーションの標的にします。
近年、治療成績が良好なカテーテルアブレーションには、頻拍を根治させることができる利点があります。
まとめ
不整脈は、脈拍リズムが速くなる、ゆっくりになる、あるいは不規則になる状態を指します。
脈拍数が1分間に40以下になると徐脈に伴って息切れ、めまいなどの症状が出やすくなりますし、反対に脈拍が1分間あたり120以上になれば病的な頻脈による動悸や息切れ、胸痛などの症状が認められます。
治療の必要がない不整脈もありますが、意識を失う、脈が遅くなって息切れがする、突然動悸がする、といった場合は治療が必要な不整脈の症状である可能性があることを知っておきましょう。