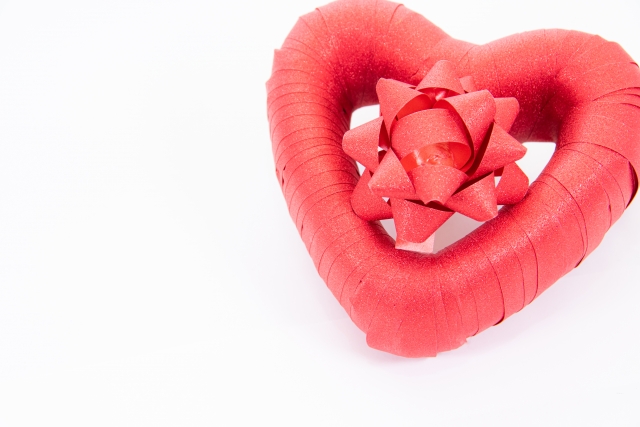酸素欠乏症が脳に与える影響と、酸素不足と関連のある病気

脳に供給される酸素の量が低下するとさまざまな影響が現れます。例えば、睡眠時無呼吸症候群では、睡眠の質が低下して日中に眠気を感じやすくなります。また、密閉された空間で生じることがある酸素欠乏症は、心疾患のある人にとっては特に危険な状態です。
ここでは酸素不足が脳に与える影響や、関連する疾患について見ていきましょう。
目次
酸素欠乏症とは

密閉された空間で物の酸化が起こると空気中の酸素濃度は低下し、酸素欠乏症が発生しやすくなります。
水分が残ったままの鉄製や銅製のタンクやくず鉄や魚油が入ったタンク、あるいは貯蔵施設や井戸の内部など酸素が消費されたタンク内や空間に入ると、酸素欠乏症に陥る危険性があります。
酸素欠乏症については、空気中の酸素濃度の低下により体内に酸素を十分に取り込めなくなった場合に起こる症状であり、空気中の酸素濃度が18%未満というのが酸素欠乏症の基準となっています。
特に、酸素濃度が16%を下回ると、有意に自覚症状が表れ始めます。
心疾患がある人の場合は、酸素濃度が16~12%でも危険な状態となることがあります。また、疲労の蓄積や貧血など体調や体質によっては、症状が現れやすくなったり重症化したりするためさらに注意が必要です。
酸素不足が脳に与える影響

脳内の酸素が不足すると、神経伝達物質であるグルタミン酸がニューロンから大量に放出され、このグルタミン酸の増加により、一酸化窒素が産生されます。
神経ニューロンや血管で産生された一酸化窒素は、ニューロンからのグルタミン酸放出を促進して、健忘(最近の記憶がなくなること)などの症状を認めることがあります。
酸素不足の状態が続くと、ブドウ糖などの酸化が行えず、エネルギーを得ることができなくなり、脳細胞が死滅することで意識障害や運動障害が起こります。
さらに、脳幹が障害されると心停止、呼吸停止など、生命維持ができなくなり死に至ります。
低酸素状態になる睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群は、眠り出すといびきをかいて知らぬ間に呼吸が止まり、日中の眠気を含めた過眠症状や高血圧などを引き起こす病気です。
睡眠時に呼吸が止まると脳や心臓、腎臓など主要な臓器に十分な酸素成分が供給されずに、高血圧や脳梗塞、慢性腎不全などを合併する危険性が上昇すると考えられています。
睡眠時無呼吸症候群が疑われる症状
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に何度も呼吸が止まり、周囲の方からいびきをよく指摘される、夜間の睡眠中に頻繁に目が覚める、起床時に頭痛や倦怠感を自覚しやすい、日中の眠気などを経験するなどの特徴を有します。
睡眠時無呼吸症候群は、いったん眠り出すと知らず知らずのうちに呼吸が止まってしまう病気であり、眠り出すとまた呼吸が止まってしまうことを一晩中繰り返すために夜間睡眠が全くとれずに日中に強い眠気が出現します。
睡眠時無呼吸症候群の方は、夜間における深い睡眠が妨げられることによって多大なストレスが蓄積されることによって、血糖値やコレステロール値が高くなることで様々な生活習慣病やメタボリック・シンドローム症候群を引き起こしやすくなります。
睡眠時無呼吸症候群になりやすい人
睡眠時無呼吸症候群を発症させる主な原因は、肥満による喉周りの脂肪であることが多いと言われています。
睡眠中は誰でものどの緊張が緩むために健常者でも空気の通り道が細くなりますが、特に肥満の方ではのどへの脂肪沈着率が増加するために更に空気の通りが悪くなります。
また、鼻中隔湾曲症の人も睡眠時無呼吸症候群になりやすいと考えられています。
鼻の穴を左右に隔てて軟骨と骨で構成されている壁構造を鼻中隔と呼んでおり、この鼻中隔が強く曲がって湾曲していることによって、鼻閉やいびきなどの症状が長期に渡って出現する病気が鼻中隔湾曲症です。
鼻中隔湾曲症は、基本的にはアレルギー反応や細菌感染などの内因性の病態ではなく、鼻中隔が物理的に湾曲しているためにいびきや鼻閉などの症状が引き起こされます。
さらに、扁桃腺が肥大している場合も睡眠時無呼吸症候群に陥りやすいと指摘されています。
扁桃腺が肥大化すると、空気の通り道が自然と狭くなって、いびき症状が引き起こされて、睡眠の質が低下するために、日中に眠気が強く襲ってきて集中力が低下することに繋がります。
睡眠時無呼吸症候群の治療
睡眠時無呼吸症候群と診断された場合には、その重症度によって様々な理学的療法や手術治療が実践されることになります。
睡眠時無呼吸症候群に対する最も重要な治療法と考えられているのは、経鼻的気道持続陽圧療法です。この治療は鼻にマスクをつけて特殊な機械で圧力をかけ、空気を送り込ませます。これによって肺への空気の循環が良好となり睡眠時に呼吸が停止することがなくなります。
経鼻的気道持続陽圧療法を実際に導入する際には、短期間入院する必要があり治療後には体調確認や機械調整を要するため、月に一度の受診が必要です。
酸素不足と関連のある病気
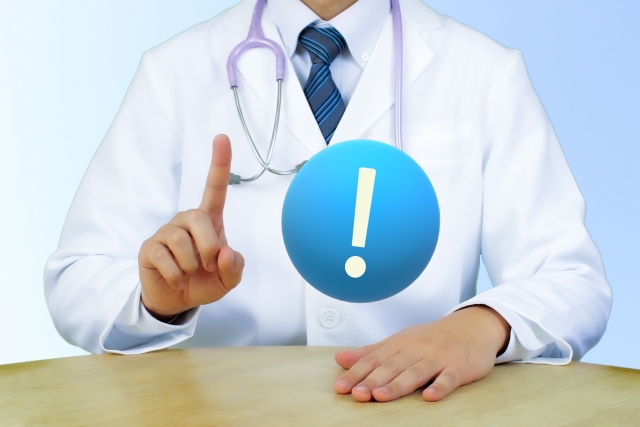
酸素不足と関連のある病気には低酸素血症と低酸素脳症があります。
低酸素血症とは
低酸素血症とは、動脈血中の酸素が不足した状態であり、酸素を取り込む「呼吸」、酸素を運ぶ「血液」、血液を循環させるポンプの「心機能」のいずれかに異常が見られることが原因です。
低酸素血症は、動脈血酸素分圧(以下、PaO2)が正常値よりも低下した状態(健常者のPaO2は90~100mmHg程度)であると考えられています。
低酸素血症が悪化して、動脈血中の酸素が不足していると呼吸回数や換気量が増えて、呼吸困難や不整脈、意識障害などの症状が出現します。
また、PaO2や経皮的動脈血酸素飽和度(以下、SpO2)の違いによって、例えばPaO2 60mmHg/SpO2 90%の場合には、息苦しさや呼吸回数の増加(呼吸不全)、PaO2 40mmHg/SpO2 75%の場合には、心虚血性変化や不整脈が出現する可能性があります。
さらに、PaO2 30mmHg/SpO2 60%の場合には、より重篤化して、意識障害や昏睡の状態に陥ると考えられます。
低酸素脳症とは
低酸素脳症による一般的な症状は、頭痛、めまい、吐き気、嘔吐、倦怠感、手足の麻痺や筋力低下、意識障害、言語障害などが挙げられます。
これらの症状は、脳への酸素供給が不足することで神経細胞の機能が低下し、脳の正常な働きが阻害されるため起こりますし、低酸素脳症の進行による重篤な症状としては、意識の混濁や昏睡状態、けいれん、失神、心不全などがあります。
重篤な状態は脳への酸素供給がほぼ停止した場合に生じ、命に関わる事態となります。
低酸素脳症の症状は個人によって異なる場合がありますので、早期に専門医に相談することが重要です。
まとめ
これまで、酸素欠乏症が脳に与える影響と、酸素不足と関連のある病気などを中心に解説してきました。
酸素欠乏症とは、空気中の酸素濃度が18%未満の状態になり、必要とされる酸素を体内に取り込めないことにより生じる症状のことを指しています。
長時間の酸素不足が続くと、脳細胞が損傷を受け、低酸素脳症を引き起こすことになります。
低酸素脳症とは、酸素供給が不十分な状態によって脳に酸素不足が起こる病態であり、脳への酸素供給が減少することで酸素濃度が低下し、脳細胞が損傷を受ける状態です。
また、夜間の睡眠の質低下や日中の眠気や疲労感などの症状が出現している際には、低酸素状態になる睡眠時無呼吸症候群が潜在化している懸念がありますので、一度専門医療機関に相談してみましょう。
今回の情報が少しでも参考になれば幸いです。