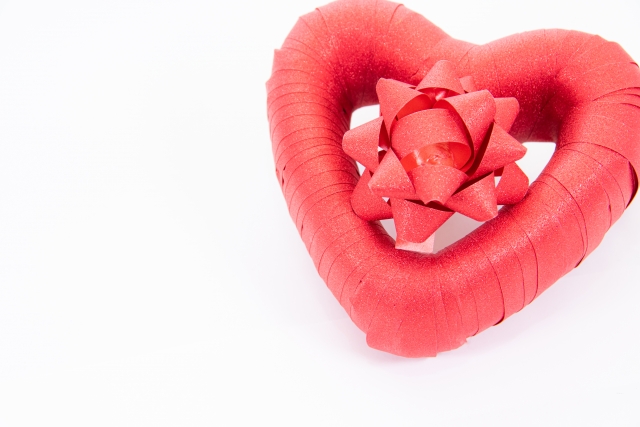体から甘い匂いがするのは糖尿病かも?体臭で分かる体の異常

体が発する臭いの中で、普通の汗の匂いではなく、何か甘い匂いがする場合は糖尿病が原因である可能性があります。他にも、様々な匂いから病気を推定することができる場合があります。ここでは糖尿病を中心に、体臭と体の異常の関係について解説します。
目次
体から甘い匂いがするのは糖尿病かも

体から甘い匂いがする場合、糖尿病が原因で起こっている可能性を否定はできません。糖尿病と甘い匂いにはどのような関係があるのでしょうか。
糖尿病とインスリン抵抗性
糖尿病は血糖値が高くなる病気ですが、この病気の特徴を説明するのに必ず必要になってくるのがインスリンというホルモンです。
体の中の糖分を維持するために、様々なホルモンが作用しています。その中でも血糖値を上げるホルモンは、何種類か存在します。様々なホルモンが低血糖に反応して作用し、色々な機序で血糖値を上昇させます。
一方で、血糖値を下げるホルモンはインスリンしかありません。インスリンは、膵臓のβ細胞から分泌されるホルモンで、血糖値が上昇してきた時に分泌が盛んに行われるホルモンです。
インスリンの働きは血糖値を下げるという風に説明しましたが、正確に言うと血液中の糖分を、細胞の中に取り込むための作用をしているホルモンになります。細胞が活動するためにはエネルギーが必要で、そのエネルギーの代表が糖分ですから、糖分を血中から細胞内に取り込むためのインスリンは非常に重要なものになるのです。
しかし、様々な原因で、インスリンがなかなか効果を発揮できなくなる状態があります。この状態はインスリン抵抗性と呼ばれ、長く続くと糖尿病を発症してしまいます。インスリン抵抗性が出てくる原因としては、遺伝や肥満、運動不足、高脂肪食、ストレスなどが関与していると言われています。
インスリン抵抗性があると、様々な細胞に対してインスリンが作用しにくくなります。すると筋肉や脂肪組織の糖の取り込み能が低下して、血液中に糖が余るようになります。そうなると血糖値が下がりにくくなり、血糖値を下げるために多くのインスリンをさらに分泌しようと膵臓のβ細胞は頑張ります。
しかし、膵臓は次第に疲弊してインスリン分泌機能の低下をまねき、血糖値がさらに上昇してしまいます。これが糖尿病の状態です。
インスリン抵抗性とケトン体の増加
インスリン抵抗性が継続すると、体の細胞は糖からエネルギーを得ることができなくなります。この状態になってくると、体は糖以外のものから細胞にエネルギーを与えようとします。そこで使われるのが、体の脂肪です。
脂肪はエネルギーのために分解されます。しかし、分解されても糖になるわけではありません。糖になる代わりにケトン体という物質になるのです。脂肪が分解されて、分子になった後、肝臓に運ばれて肝臓で合成されます。ケトン体にはアセト酢酸や、3-ヒドロキシ酪酸、アセトンなどが存在しています。このうち特に、アセト酢酸や3-ヒドロキシ酪酸が栄養源として使用されます。
ケトン体は脂肪の分解によって生成されるものですから、ダイエットの時には脂肪も減って、エネルギー源にもなり、一石二鳥と考えるかもしれません。しかし、ケトン体が病的に増加することにはリスクがあります。
ケトン体は、酸性の物質です。ですのでケトン体が血中に増加すると、血液が酸性に傾きます。少量であれば問題ありませんが、インスリン抵抗性が非常に強くなった時など、病的にケトン体が増え、強く酸性に傾いてしまいます。この状態を、ケトアシドーシスと言います。
ケトアシドーシスになると、体の様々な機能が不安定とになり、脱水も非常に強くなります。結果として、ふらつきなどから始まり、ひどい場合には意識障害や死に至ることもあります。
ケトン体の臭いの特徴
ケトン体の匂いの特徴は、甘い匂いです。糖尿病の初期は甘い匂いがして、進行すると甘酸っぱい匂いになるとも言われています。この匂いの原因がケトン体なのです。ケトン体の中でも特にアセトンという物質が、気化しやすいので臭いの原因となります。
糖尿病が初期の場合には、ケトン体も薄いため、甘い匂いで済みますが、だんだんと病状が進行するに従って臭いがきつくなり、甘酸っぱい匂いになると考えられています。
体臭で分かる体の異常
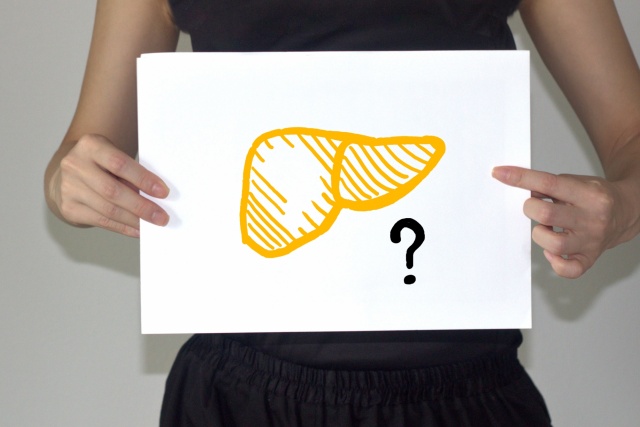
糖尿病の他にも、様々な病気で体の匂いが変化します。体臭から分かる体の異常にはどのようなものがあるのでしょうか。
肝機能低下(アンモニア臭)
肝臓の機能が低下してくると、アンモニアのような臭いがしてくると言われています。
もともと体の中ではタンパク質を分解する時にアンモニアが生成されていますが、そのアンモニアを分解しているのは肝臓です。従って、肝臓の機能が低下すると、肝臓でアンモニアは分解しきれなくなるため、臭いが出てくるのです。
アンモニアのような臭いがする場合には、まず肝臓に何らかの異常がないか調べることが必要です。肝炎などがあれば治療が必要になってきます。
そのようなものがない場合には、種々の対策があります。
まずオルニチンを摂取するといいです。オルニチンは体の中でアンモニアと反応することによって、無害な尿素に変換され、尿から排泄されます。オルニチンはしじみやえのき、ひらめなどに多く含まれています。
また飲酒量を減らすのも大切です。アルコールは肝臓で代謝されます。アルコールを多く取ると、アンモニアを分解する肝臓の能力がアルコールの分解に取られてしまい、アンモニアが上昇してしまいます。
胃腸機能低下(腐敗臭)
胃や腸の機能が低下することによって、腐敗臭がすることがあります。
摂取した食べ物は消化管で消化分解されて、吸収されます。残りカスは大腸へと送られて、腸内細菌叢によって分解されて便となります。しかし、便の流れが悪くなると、排泄物が腸に長く留まってしまいます。このように腸に長く排泄物がとどまると、腸内細菌層のバランスが乱れて、悪玉菌が増加します。
悪玉菌は便の中の様々な物質を分解して腐敗物質を作り出します。インドール、スカトール、メチルメルカプタン、硫化水素、アンモニアなど、様々な匂いの原因となる物質ができてしまうのです。
これらの物質も便通があれば、便と一緒に外へ排泄されます。しかし、長く便が腸の中にとどまると、腸の中にある腐敗物質は腸壁から吸収され、血液中に溶け出します。これが全身へと運ばれ、汗腺や口腔から外に出ることによって、体臭や口臭になります。
生活習慣病(加齢臭)
40代頃から増加する加齢臭も体の匂いの一つとして挙げられます。
加齢臭の原因となるのは、皮脂の成分であるパルミトレイン酸が酸化することによってできる、2-ノネナールという物質です。皮脂が多いと、その代謝性物質である臭いの元となるノネナールも増加し、臭いが強くなります。
皮脂が増加する生活習慣としては、まず食事生活として動物性脂肪の取り過ぎが考えられます。脂質を多く取ればそれだけ皮脂は多くなります。他には糖分が多い食べ物や飲み物を取ると、インスリンが多く分泌され、ブドウ糖が中性脂肪に変化する量が多くなります。
一方、青魚に含まれるEPAやDHAは中性脂肪を下げる働きがありますし、ビタミンB2、B6には、皮脂の分泌量を減らす作用があります。これらの物質を摂取する量が少ないと体臭が強くなります。
また、汗をかくということも大事です。あまり汗をかかわない人は汗腺が衰え、ベタベタとした臭いが強い汗をかきやすくなって加齢臭がひどくなります。汗をかいたときは、こまめに拭き取るようにしましょう。