放置するとどうなる?胃潰瘍の症状とステージ分類
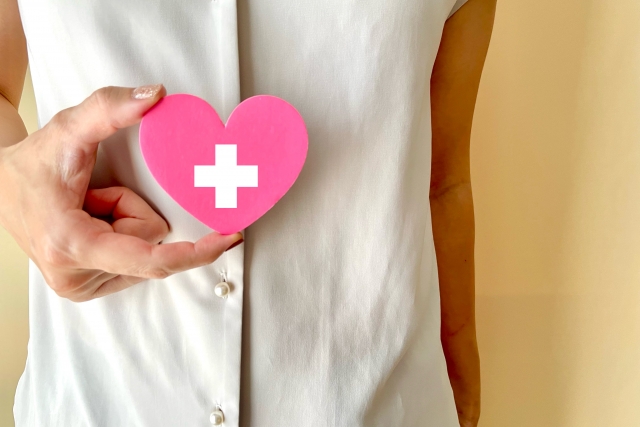
胃潰瘍という疾患はストレスや薬物などが原因で発症することが多く、現代社会における代表的な病気であるといえます。
胃液中に含まれる塩酸やペプシンといった物質が、過剰に産生されて胃を保護している消化管粘膜を消化してしまう、あるいは胃粘膜を防御している因子が減弱してしまうことによって胃壁に潰瘍性病変を形成します。
ここでは胃潰瘍の症状と病期ステージ、放置した場合の合併症のリスクについて解説します。
目次
胃潰瘍の症状

胃潰瘍の代表的な症状には次のものが挙げられます。
みぞおちの痛み・腹痛
胃潰瘍における自覚される症状の約9割は腹痛で、そのほとんどが上腹部のみぞおち周囲に感じる腹痛です。基本的には食後に痛みが出現しやすく、食事を過多に摂取しすぎると長時間に渡って腹痛が継続します。
一方で、胃潰瘍に罹患しても全く症状を感じないケースもあります。自分で気がつかないまま、知らず知らずのうちに潰瘍が悪化して胃に穴が空いて穿孔を引き起こし、腹部の激痛で初めて胃潰瘍が発見される場合もあります。
吐き気、嘔吐
胃潰瘍では胃粘膜が胃酸などによって傷つけられて、吐き気や嘔吐症状を引き起こします。
胃潰瘍になると、胃の粘膜が強い炎症を起こすために、胃の痛み以外にも腹部不快感、吐き気、嘔吐など多彩な症状を呈することが予想されます。
さまざまな原因によって胃液や胃酸が多く分泌されすぎて胃粘膜の防御機能が崩れて胃潰瘍を発症すると、胃液が食道に逆流することで惹起される胸焼けを自覚するのみならず、嘔吐や吐き気などの症状が出現して生活の質が低下することが知られています。
体重減少・食欲不振
ダイエットをしているわけでもないのに体重減少する、以前と比べて食欲が低下して体重が下がり始めた、いつも通りの食事を摂取しているが直近の半年で5kg程度痩せた、といった場合には身体のどこかに異常所見が潜んでいる可能性が考えられます。
ダイエットしていないのに普段よりも顕著に体重減少が認められる際には、胃潰瘍を始めとする消化管疾患が隠れていることが懸念されます。体重の約5%以上の減少率に加えて基礎疾患による食欲不振など他のサインが出現する場合は注意が必要です。
特に胃潰瘍では、随伴する症状としてみぞおち周辺の痛みや胃もたれ、胸焼け、吐き気、嘔吐といったさまざまな症状が重なることでさらに食思不振に繋がりやすく、食事量が低下することによって体重が減少する傾向があります。
吐血

胃潰瘍を発症した場合には、胃酸と共にどす黒くなった血液成分を吐血することがあります。
このようなケースは出血性胃潰瘍と呼ばれており、潰瘍が認められる部位の血管が破裂するのが原因であり、出血して吐血した際には冷や汗、頻脈、血圧低下、腹部の激痛を自覚することもあります。
そもそも胃潰瘍とは、胃酸などをはじめとする消化管に対する攻撃因子が増強されることで胃粘膜に深い傷が形成され、粘膜の下の組織である筋層レベルにまで粘膜損傷が達している状態を指しています。
潰瘍病変部位は肉眼で観察するとくぼみ状になっており、粘膜が損傷されていく過程で血管が露出して、その露出血管から出血をきたすと吐血して血液を嘔吐することにつながります。
下血・タール便
胃潰瘍に罹患したときに、どす黒いベタベタしたタール便や下血症状が認められることもあり、吐血時と同様に潰瘍部位における露出血管が破綻することが直接的な原因です。
日常生活において黒色様を呈する便を排便したことに自分自身で気づかないこともあり、貧血症状が進行してはじめて胃潰瘍の存在を疑う場合も往々にしてあります。
下血やタール便の兆候は、胃潰瘍以外にも胃や大腸における悪性腫瘍でも認められる可能性がある症状なので、タール便が継続して発見されるケースや大量に下血した場合などは専門医療機関で精密検査を実施する必要性が高いと考えられます。
貧血症状
血液中の赤血球量が減少すると、それぞれの臓器に向かってヘモグロビンを介して酸素供給するのが不十分になり、貧血の状態となります。貧血状態では、主にめまいや疲労感、倦怠感、動悸、息切れなど多彩な症状を呈します。
胃潰瘍は過労やストレス、ピロリ菌や特定の薬物によって胃の粘膜が炎症を起こして一部が欠損して障害される病気です。進行すると病変部から出血を引き起こして吐血や下血が認められ、それらに伴って出血による貧血症状が出現することが知られています。
実際の診療場面では、問診、身体診察、血液検査所見などから貧血を認めた際には下血や吐血などの症状有無を入念に調べ、必要に応じて上部消化管内視鏡検査などで胃の粘膜状態を観察して評価します。
胃潰瘍のステージ分類と症状

胃潰瘍の病期ステージは次の3種類に大きく分類されます。
- 活動期(active stage)
- 治癒過程期(healing stage)
- 瘢痕期(scarring stage)
それぞれをさらに2段階に大別することによって6つのグループに分かれます。
通常では、胃潰瘍を発症してからA1→A2→H1→H2→S1→S2の順番で徐々に治癒していく過程が認められます。
胃潰瘍急性期(A1・A2)の特徴と症状
A1ステージは潰瘍が活発に活動している病期を意味しており、発症直後の潰瘍のために潰瘍部に血塊や出血性病変が指摘でき、潰瘍の周辺粘膜部は浮腫状に膨らむと共に潰瘍底部に汚れた白苔が認められます。
少し潰瘍が改善すれば、A2ステージに移行して、潰瘍底が白苔に覆われるにつれて血塊成分や活動性出血を認めなくなり、病変部位辺縁の浮腫性変化も減衰しますが、患部周囲には発赤所見を軽度認める状態になります。
胃潰瘍治癒期(H1・H2)の特徴と症状
発症間もない胃潰瘍急性期Aステージを乗り越えると、治癒過程期(Hステージ)に入ります。
H1ステージでは、潰瘍部が小さくなり、潰瘍辺縁の浮腫は消失して赤色様の粘膜上皮が再生されると同時に白苔は薄くなり、患部周囲には粘膜襞の集中所見が認められることもあります。
H2ステージになると、さらに潰瘍病変部が縮小化して再生された上皮組織が顕著となり治癒がかなり進んだ潰瘍であるといえます。
胃潰瘍瘢痕期(S1・S2)の特徴と症状
胃潰瘍の急性期、また治癒過程期を過ぎると胃粘膜が瘢痕性変化を呈することになります。
S1ステージでは、潰瘍病変や白苔そのものは消失して、赤色の再生上皮によって被覆された瘢痕組織となり潰瘍部位は概ね軽快した状態となります。
S2ステージになると、さらに発赤所見が消失して白色の瘢痕となり、潰瘍形成された部位の瘢痕組織にはわずかな再生上皮しか認められない治癒状態となります。
反対に、再度胃潰瘍が再発して悪化する場合にはA2からS2までの全ステージからA1分類の状態になるとされています。
放置するとどうなる?胃潰瘍の合併症

胃潰瘍を放置して悪化すると、次のような合併症につながります。
穿孔(せんこう)
胃潰瘍の痛み症状を放置すると、胃壁に穴が空く場合があり(穿孔)、再発を繰り返すと胃が変形する、あるいは胃の動きが悪くなって機能不全や消化不良、胃もたれなどの症状につながることが示唆されています。
胃潰瘍の治療の基本は薬による内科的治療であり、手術の対象となることは現在ほとんどありませんが、潰瘍が未治療で経過した場合、まれに孔が空いて穿孔といわれる状態に至ることがあります。
胃穿孔は発症すると急激におなかが痛くなり、放置すると腹膜炎になり命にかかわる危険な病気です。
胃潰瘍が穿孔した場合、炎症の広がりが限局的で、症状が軽い場合は、絶食で症状が改善する場合もありますが、多くの場合、腹部全体に炎症が波及しており、救急車で運ばれて緊急手術になることが多いです。
大量の出血
胃潰瘍は、胃液という強い酸の刺激によって、胃の組織が剥がれ落ち、内部からえぐられた状態です。
本来、胃は塩酸やペプシンなどの消化液を分泌して、食べ物の消化を行っていますが、この胃液が何らかの原因で、胃の組織をも溶かして消化してしまう疾患が胃潰瘍です。
胃潰瘍が進行した場合には、出血を伴うことがあり、大量に出血すると、ショック状態に陥ることもあります。
胃潰瘍からの出血が多くなると、吐血や下血を起こすこともあります。
基本的に、血液は、胃酸で参加されると黒色~褐色に変色するため、吐血ではコーヒー様の吐物となり、下血では黒い色に変色します。
胃潰瘍が進行した症状としては、上腹部痛が最も多く、潰瘍部分から出血すると吐血や黒色便がみられます。
胃潰瘍から下血する場合、タール便と言って、コールタール様のどす黒い便が出ることが多く、出血をきたした場合、痛みが無いこともありますので、自覚的な症状が無いからといって心配ないとは言えません。
幽門狭窄
胃の出口のことを幽門部といい、何らかの原因で幽門部が狭窄してしまい、胃の内容物(食べ物や胃液など)が十二指腸へ流れていかないことを幽門狭窄症といいます。
胃潰瘍により、幽門が狭くなると、食べ物の通過障害が起きます。
幽門狭窄の代表的な症状は、「げっぷ」、「嘔吐」、「おなかが張る」などがあり、食べ物などが流れないことが症状の原因なので嘔吐すると楽になることも特徴のひとつです。
進行しても胃がんにはならない
胃潰瘍が進行しても、原則直接的に胃がんの発症原因にはなりません。
以前は、慢性の胃潰瘍が胃がんになると考えられていた時期もありましたが、現在はそのような可能性は低いことがわかっています。
ただし、胃がんの発生する場所は胃潰瘍の発生しやすい部位と一致していますので、まったく無関係というわけではなく、胃潰瘍や胃炎などの刺激が長期間続くと、胃がんができやすくなる可能性があります。
ちなみに、早期の胃がんは、潰瘍性病変を作ることがあり、内視鏡で観察しても胃潰瘍と区別することが難しい場合が少なくありません。
まとめ
胃潰瘍の症状とステージ分類などを中心に解説してきました。
胃潰瘍は、以前は男性に多く発症する病気でしたが、近年では女性や若年者の発症率も高くなり身近な疾患として認識されています。
胃潰瘍が発症すると、各々のケースでみぞおち周辺の心窩部痛、嘔気、嘔吐、食欲低下、体重減少、吐血や下血などさまざまな症状が認められます。
胃潰瘍は潰瘍が形成されてから改善していくそれぞれのステージごとに活動性を認めるA(active)ステージ、治癒過程を示すH(healing)ステージ、治癒して瘢痕期に変化するS(scaring)ステージの3種類に分類されています。
胃に関する正確な診断や胃潰瘍の病期分類、進行度を確定させるには、胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)を施行することが必要です。胃カメラによって胃がんなどの悪性腫瘍との鑑別も可能となるため、心配な症状をお持ちの方は早めに消化器内科など専門施設に相談しましょう。
今回の情報が少しでも参考になれば幸いです。





