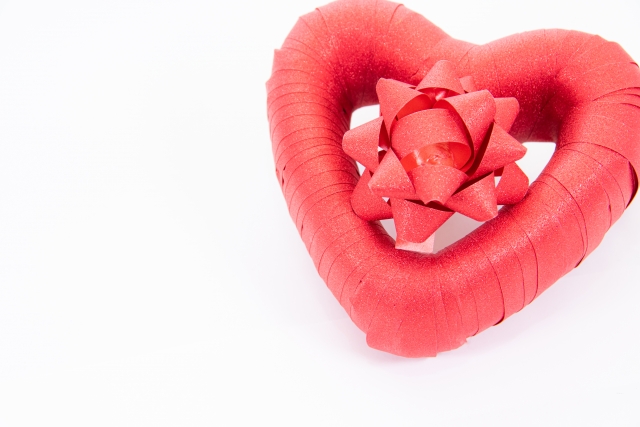高齢者の息切れの原因は?老化の影響と考えられる病気

年齢を重ねると、だんだんと息切れの症状が出てくることが多くなります。老化によって呼吸の能力が落ちてくることで息切れをすることもありますが、何らかの病気が隠れていることもあります。ここでは息切れに注目し、老化の影響や、考えられる病気の可能性について解説します。
息切れはどのような事が原因で起こってくる?

息切れと言うと、肺などの呼吸器の問題というイメージがあるかと思います。確かに肺に病気がある場合には、息切れの症状が起こってくることはよくあります。しかし、肺に病気があっても肺全体の機能が落ちていなければ息切れの症状は起こってこないことが多いですし、反対に肺に全く問題がなくても息切れの症状が起こってくることもあります。
では息切れとはどのような症状なのでしょうか。
そもそも人は、空気を吸い込んで吐いてという呼吸の運動をすることによって、酸素を取り込んで二酸化炭素を排出するということを繰り返しています。それを行うのが肺です。肺では、空気中の酸素を血液中に取り込み、血液中に溶け込んでいる二酸化炭素を空気中に排出します。
血液中に取り込まれた酸素は、赤血球にあるヘモグロビンに結合します。ヘモグロビンは血液の流れによって全身へと向かい、全身の細胞へと酸素を供給します。
この一連の流れが、どこかで滞ることがあると、体を動かした時などに細胞に酸素が不足し、息切れの症状が出るのです。つまり、呼吸ができない時だけではなく、呼吸はきちんとできているのに体中に酸素が届けられない時や、酸素の運搬に何らかの異常がある時にも息切れの症状が出てきます。あるいは、精神的な問題によって、息が苦しいと感じることもあります。
老化の影響による息切れ

一般的に、内臓の機能が低下していなくても、老化をしてくるとだんだんと息切れの症状が出てきます。
年齢を重ねると筋力が低下してきます。筋力が低下してくると特に呼吸の筋肉の力が低下してきて、酸素を取り込む能力が低下してきてしまいます。また、背骨が曲がってきたりすることによって、だんだんと胸の形が変形し、呼吸を十分できなくなることも息切れの原因として重要なものとなります。
高齢で息切れを感じる人の多くは、1つの臓器や1つの筋肉だけの影響によってではなく、いくつもの臓器の不調が積み重なり、それぞれの臓器の不調はそんなに大きくないのに、体全体では大きな変化となって息苦しさを感じるようになってくるのです。
息切れの原因になる病気

息切れの症状の背景に病気が隠れている可能性も否定はできません。息切れをきたすような代表的な病気を確認しておきましょう。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
肺の機能は、息を吸うことと考えられがちですが、実は息を吸うのは肺自体の力ではありません。息を吸う時には、肺の周りの骨が筋肉によって動くことによって、肺を外から引っ張って広げることによって、息を吸っています。
肺が自分自身の力で動くのは、息を吐く時です。肺は肺胞という非常に小さな風船のような形をした構造を無数に持っています。この肺胞の壁には弾性繊維という自動的に縮む力を持っている繊維が含まれています。息を吸って引き伸ばされた後は、この弾性繊維が縮むことによって肺はしぼみ、息を吐くことができます。
しかし、長年にわたって喫煙をすると、肺胞の壁が壊れてしまいます。そうなってしまうと、肺全体の弾性繊維の量も減ってしまいますから、しぼむ力が弱まってしまいます。つまり息を吐く力が弱まってしまうのです。
このように、長年の喫煙によって肺がしぼみにくくなる状態のことを、慢性閉塞性肺疾患と言います。
息を吐き出そうとしてもなかなか吐き出せなくなるため、息苦しさを強く感じるようになってしまうのです。
過換気症候群
過換気症候群は、一般に過呼吸と呼ばれる症状です。
息を吸っても酸素が足りないと感じてしまい、非常に頻回に呼吸をしてしまう状態を言います。頻回に呼吸をすると、酸素の取り込みには問題がないのですが、二酸化炭素の排出が過剰になり、血液中の二酸化炭素の値が低下してしまいます。これによって、手がしびれるなどの様々な症状が出現してきます。
昔はペーパーバック法と言って、袋を口に当てることによって吐いた二酸化炭素を再び吸入する対処法が提唱されていましたが、現在では吸入酸素濃度が低下してしまう可能性があるということで、しない方がいいとされています。
ゆっくりと安静にできる場所で、1回1回の呼吸をしっかりとすることによって対処します。
間質性肺炎
間質性肺炎というのは、肺胞の壁の内側の部分で炎症が起こり、壁が分厚くなってしまう状態を言います。
壁の中には毛細血管が走っていて、この壁を通過して酸素や二酸化炭素のやり取りがされます。しかし、炎症が起こって壁が分厚くなってしまうと、酸素の取り込みが阻害されて低酸素血症になります。二酸化炭素のやり取りには大きな問題がないとされています。
重症にならなければ、日常生活を行う程度で低酸素になることはあまりありません。しかし、体を動かして酸素の必要量が増加すると、息苦しさを感じることが多くなってきます。
間質性肺炎が起こりやすいのは、膠原病を発症した時や、一部の薬剤を使用した時などです。
心不全
心不全は、心臓の機能が低下した状態を言います。心臓はかなり複雑な構造ですから、多くの種類の心不全があります。
高齢になってくると、心臓の機能がだんだんと落ちてくることもありますし、高血圧の影響で心臓が肥大してくることもあります。あるいは、心筋梗塞などによって、心臓にダメージがあることによって心臓の機能が落ちることもあるでしょう。
いずれにしても、血液を送るポンプの役割である心臓の機能が低下してしまいますから、全身に血をめぐらせることが不十分となり、少し動いただけでも息切れの症状が起こってくることはよくあります。
貧血
貧血は、血液中の赤血球が減少し、酸素の運搬能力が低下した状態です。
もともと赤血球の産生は、腎臓から分泌されるエリスロポエチンというホルモンが、骨髄に赤血球を作るように指令を伝えることによって行われます。しかし高齢になってくると、腎臓の機能が低下するとともにエリスロポエチンの分泌が低下し、貧血になることがよくあります。そうでなくても、骨髄の造血能が低下することによっても貧血は進行します。
また、血液を作る能力が低下するだけではなく、出血によって貧血が起こってくることもあります。胃潰瘍からの出血や、色々な場所にできているポリープからの出血によって、貧血が起こってくることがあります。
貧血が起こってくると、眼瞼結膜の赤みが失われ、白っぽくなります。内科の診察でまぶたの内側を見ているのはそのためです。もし貧血が疑われるようであれば、早めに内科を受診して診察を受けておくといいでしょう。