急性と慢性の違いは?肺血栓症と慢性血栓塞栓性肺高血圧症

エコノミークラス症候群としても知られる深部静脈血栓症では、下肢の静脈深部に血栓ができます。この血栓が肺の血管を詰まらせると肺血栓塞栓症を引き起こします。
ここでは肺血栓塞栓症の特徴と、慢性化した際に合併する慢性血栓塞栓性肺高血圧症について解説します。
血栓症とは

血栓症とは、何らかの原因によって血液が固まって血栓になり、それによって血管が詰まってしまう病気の総称です。
血栓によって血管が詰まると血流が阻害され、各部位や臓器に栄養が行き届かなくなる結果、機能障害が発生したり、各組織の壊死が引き起こされたりします。
肺塞栓症とは

肺塞栓症は、肺の血管に血栓が詰まることで、突然の胸の痛みや呼吸困難などが起こります。
症状の強さは、血栓の大きさによってさまざまです。小さい血栓の場合は症状が出ないケースもありますが、大きな血栓の場合には血流が止まりショック状態に陥ったり、失神発作を起こしたりすることもあります。重度の場合には、死に至ることもあります。
長時間足を動かさないでいると、血流が悪くなり下肢の静脈深部に血栓ができることがあります。これを深部静脈血栓症と呼び、この血栓が血流に乗って流れ、肺動脈に詰まることによって起こるのが肺塞栓症です。
飛行機のエコノミークラスの狭いスペースに長時間座っていることが原因になることも多く、エコノミークラス症候群とも呼ばれます。
長時間同じ姿勢でいることで肺塞栓症のリスクが高まります。特に、手術後などで安静を余儀なくされている方は、血栓ができやすくなることがあるため肺塞栓症になりやすいといえるでしょう。また、妊娠中の方や子宮筋腫のある方も腹部の静脈が圧迫され、血栓ができやすくなります。
さらに、悪性腫瘍のある方や体質によって血が固まりやすい方も、肺塞栓症のリスクが高いとされています。
肺塞栓症の症状である呼吸困難や胸の痛みは、多くの場合には突然発症するため、肺動脈に血栓が詰まる前兆は見極めるのが難しいといえるでしょう。
下肢に血栓ができている場合はふくらはぎや太ももに腫れ・むくみ・痛みなどを感じることがあります。
肺血栓塞栓症とは

肺血栓塞栓症とは、足や下半身などにできた血液のかたまりである血栓が、血流に乗って肺の血管につまり、胸痛・呼吸困難・循環不全などをきたす病気を総称して呼んでいます。
生体内において静脈(心臓に戻る血液が通る血管)の血流が悪くなって血液がよどむと、静脈の血管内に血栓ができて停滞することになります。
この血栓が、なんらかのきっかけによって血管壁から外れて、静脈を通って心臓に戻ると、肺動脈(心臓から肺へ向かう血管)がつまることがあります。
足にできた血栓は歩行動作などを契機にして、突如として血液の流れに乗って肺まで到達することがあり、この際に肺に到達した血栓が肺の血管を塞ぐと、胸の痛みや息切れなどの症状が現れるようになります。
肺血栓塞栓症は、飛行機のエコノミークラスへの搭乗によってのみ起こるわけではなく、仮に狭いところで座ったままで長時間過ごして足を動かすことが少なければ、どこでも発生する可能性があるといえます。
例えば、お腹のなかに巨大な腫瘍(卵巣嚢腫、子宮筋腫など)がある、あるいは出産後である、そして足の筋肉が弱くなることで血流が悪くなるなどが原因として挙げられます。
長時間にわたる車の運転や車中泊、さらに災害時の避難所への滞在やデスクワーク中でも肺血栓塞栓症を予防する必要があります。
急性と慢性の違い
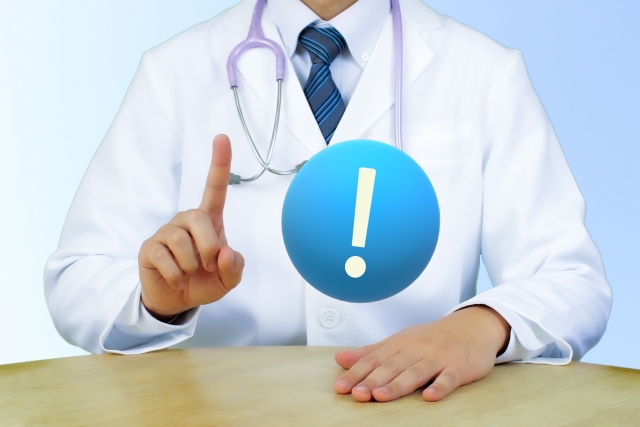
肺血栓塞栓症には急性と慢性があり、慢性肺血栓塞栓症は肺高血圧症を合併することがあります。
急性肺血栓塞栓症とは
急性肺血栓塞栓症は、心臓から肺に血液を送る肺動脈に血栓が急に詰まるために起こります。
血液の流れが停滞すると凝固して血栓ができやすくなります。
航空機などで長時間座っていて脚の血液がうっ滞して、血栓が生じて発症するエコノミークラス症候群が有名です。また、大きな手術の後や重い病気で寝ている時間が長くなると発症しやすくなりますし、それ以外にも、遺伝、様々な疾患、薬剤、加齢などによっても血栓が出来やすくなります。
血栓は主に脚の静脈の中で血液が凝固して生じ(深部静脈血栓)、血液の流れに乗って心臓を経由して肺に詰まります。
大きな血栓が肺動脈を塞ぐと、酸素を血液に取り込めなくなったり、心臓から血液を押し出せなくなり、突然死の原因にもなることがあります。
慢性血栓塞栓性肺高血圧症とは
肺動脈に血栓ないしは塞栓ができて、肺動脈の圧力(血圧)が異常に上昇するのが慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)です。
肺動脈の圧力が上昇する理由は、血栓ないしは塞栓が、肺の太い血管、さらには細い血管につまり、異常に狭くなり、また固くなるために、血液の流れが悪くなるからです。
必要な酸素を体に送るためには、心臓から出る血液の量を一定以上に保つ必要があります。狭い細い血管を介して、無理に血流を送るように心臓が努力するために、肺動脈の圧力(血圧)が上昇するといわれています。
有効な治療法の研究開発のため、慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)は難治性呼吸器疾患(指定難病)に認定されています。
まとめ
これまで、肺血栓症の概要と慢性血栓塞栓性肺高血圧症との違いなどを中心に解説してきました。
肺血栓塞栓症は、突然の呼吸困難や胸の痛み、重症の場合には心停が起こりうるような危険を伴う病気であるため、通常は入院による治療が必要となります。
入院期間は重症度や再発のリスクなどによって異なりますが、肺血栓症だと疑われる症状が出た場合には必ず入院して検査や治療が行われると思っておきましょう。
急性肺血栓塞栓症の症状は、突然にはじまる息苦しさや胸痛で、重症例では失神、血圧低下をきたします。脚のむくみや痛みが先行することもあります。原因のほとんどが脚の静脈血栓ですが、肺動脈に詰まるまで脚の症状が出ない場合も少なくありません。
一方で、慢性血栓塞栓性肺高血圧症は、器質化した血栓により肺動脈が慢性的に閉塞を起こし、肺高血圧症を合併して、臨床症状として労作時呼吸困難などを強く認める病気です。
今回の情報が少しでも参考になれば幸いです。





