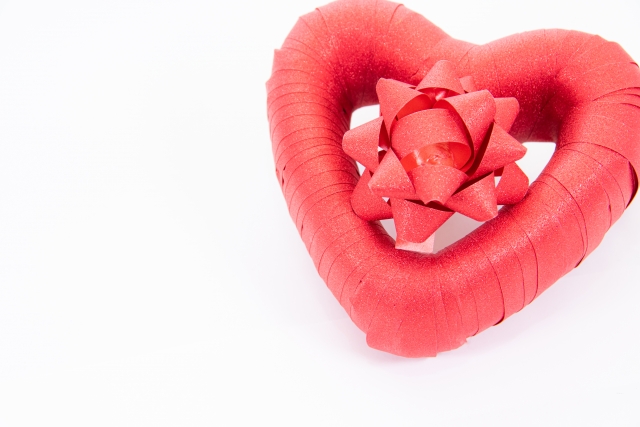痙攣の種類と原因…間代性痙攣と強直性痙攣の違いとは?

痙攣というと、日常生活をしていて手や足がピクピクと動くものだと思うかもしれませんが、なかには体全体が大きくガクガクと震えるような痙攣もあります。
ここでは痙攣とはどのようなものなのか、また、どのような種類や分類があるのかについて解説します。
痙攣の定義とは

痙攣とは、筋肉が急激に自分の意志とは関係なく収縮する発作のことをいいます。一部の筋肉のみに起こる場合もありますし、全身の筋肉に起こることもあります。ただし、全身の筋肉のなかでもの横紋筋という種類の筋肉にしか起こりません。
全身にある筋肉は大きく分けて3種類あります。腕や足を動かしたり表情を作ったりといった、意識的に動かすこともできる筋肉のことを横紋筋と言います。一方で、内臓を動かす筋肉もあります。このような筋肉を、平滑筋と言って、平滑筋は自分の意思で動かすことはできません。3つ目の筋肉が、心筋です。心筋は自分自身の意識で動かすことはできませんが、構造的に横紋筋と同じような構造をしているため、特別な扱いをされています。
このことから、痙攣の定義というのは、自分自身の意思に反して動くということですから、横紋筋のみに当てはまるものということになります。
では筋肉の収縮は、どのように起こるのでしょうか。筋肉が収縮するのは脳からの命令によります。脳の中でも、筋肉を動かす働きをする神経細胞が集まっている部分の細胞が興奮すると、その刺激は神経から筋肉に伝わります。筋肉は神経の刺激があると収縮します。
痙攣が起こるのは、この筋肉の収縮のどこかで異常な刺激が起こることによります。
痙攣の発作が起こると、発作が起こった部位や持続時間によっても変わりますが、収まった後も様々な症状が起こることがあります。意識障害が起こることもありますし、嘔吐や尿失禁、便失禁などが起こることもあります。頭痛や疲労感、意識の混濁、四肢の脱力感などが残る場合もあります。
痙攣が長時間持続する場合や、短時間のうちに何度も生じることを痙攣の重責状態と言います。この状態では、筋肉の収縮が非常に頻繁に起こるため、酸素の必要量が異常に上昇しますから、速やかに治療する必要があります。
痙攣の種類と分類

痙攣には種類があり、いくつもの分類法があります。
間代性痙攣と強直性痙攣の違い
痙攣の起こり方によって分類する方法が、間代性痙攣と強直性痙攣です。
間代性痙攣は筋肉が収縮したり弛緩したりということを交互に引き起こす状態のことを言います。力が入って緩んでを繰り返すということです。しかも、この収縮と弛緩は、ある程度時間的に周期性を持っていることが多く、収縮した時間と弛緩した時間が定期的にやってくるのが特徴です。周期が短いと、ガタガタと震えるような状態になります。
一方、強直性痙攣は筋肉が収縮したまま弛緩しない状態を言います。収縮する場所によっては関節が曲がったままになる場合もありますし、反対に関節が伸びた状態をずっと維持する場合もあります。
また、これら2つを混合した強直間代性痙攣というのもあります。ある一部分では強直性の発作が起こり、ある一部分では間代性痙攣のようなガクガクした様子が見られるといった場合もあります。
てんかん性と非てんかん性の違い
続いての分類は、てんかん性痙攣と非てんかん性痙攣です。
てんかんというのは、脳の細胞が異常に興奮することを言います。特に何らかの誘因があるわけでもなく、突然発症します。また、繰り返すことが特徴です。1回のみの発作ではてんかんとは見なされません。
筋肉の収縮を支配する脳細胞が異常に興奮することで、痙攣が起こってきます。しかし、筋肉の収縮を支配する脳細胞だけに異常が起こると限定されるわけではありません。意識を司る脳細胞に異常が起こって、意識の障害が起こる場合もありますし、その他様々な症状が起こってくるのが特徴です。
てんかんの中にも、分類があります。特発性てんかんと症候性てんかんです。
特発性てんかんは、特に原因がわからないものです。多くのてんかんがこれに分類されます。一方で症候性てんかんは、何らかの器質的な異常があることによって脳細胞が刺激され、異常な運動をしてしまうものです。構造的に異常があるとか、脳梗塞の後遺症、脳腫瘍があるなどの様々な脳疾患が原因となります。
一方の非てんかん性痙攣は、そのようなてんかんを除いた痙攣のことを指します。脳炎や髄膜炎などの感染症や頭部外傷、薬剤、血液の浸透圧の異常など、脳に対する外的な刺激によって脳が反応して痙攣することが多いです。
小児によく起こる熱性痙攣は、発熱という外的因子が脳に作用することによって痙攣が起こる、非てんかん性痙攣とされています。
全般発作と焦点発作
続いての分類は、全般性発作と、焦点発作という分類です。主にてんかんの時に用いられる分類になります。
全般発作というのは、全身に発作が起こることを言います。意識を失うだけの発作の時もありますが、全身の筋肉に痙攣が起きることが多く、発作中や発作後の合併症も多い発作になります。
焦点発作というのは、体のある一部分だけに発作が起きるものを言います。ピクピクと筋肉が収縮する場合や、手を動かそうとしても手が固まってなかなか動かないという状態がこのような発作に含まれます。
痙攣の原因の一例

痙攣の原因はどのようなものかという観点から、痙攣は脳性と脳外性に分類されます。
脳性
脳性の痙攣は、その名の通り、脳に原因があることによって起こってくる痙攣です。
例えば脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害や、脳腫瘍、頭部外傷による脳挫傷、感染症に加えて、てんかんも脳自体に問題があるので脳性痙攣とされます。
脳性痙攣の場合には、痙攣の発作を抑えるために様々な治療が考えられます。脳出血や脳腫瘍など、何らかの物理的な要素によって脳神経が圧迫されている場合には、手術によって圧迫を解除することによって、痙攣が収まる場合があります。
感染症であれば、感染症に対する治療が行われます。抗生物質や抗ウイルス薬などを投与し、感染を抑えることで痙攣の治療を行っていきます。
特発性てんかんの場合には、そのような治療介入は難しくなります。そこで使用されるのが、抗てんかん薬です。多くの種類がありますが、発作の種類や、てんかん発作の分類などによって使い分けをします。
脳外性
脳外性の痙攣は、脳以外の要素によって痙攣が起こっているものを言います。
代表的なものは熱性痙攣です。他には、低血糖や電解質の異常、尿毒症や肝不全などの何らかの中毒症状、低酸素脳症などが挙げられます。
これらの脳外性の痙攣の場合には、脳自体が悪いわけではありませんので、原因となる疾患の治療をする必要があります。原因となる疾患が治療されると、痙攣の発作が起こらなくなることがほとんどです。