狭心症の検査をすべき自覚症状と検査の種類…血液検査・心電図・カテーテル検査など
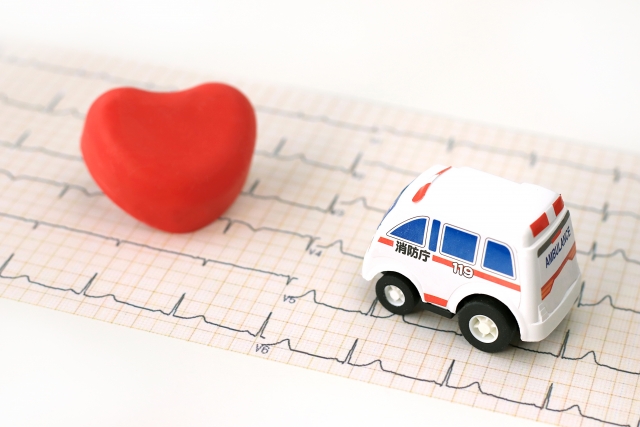
冠動脈は、心臓を構成する筋肉である心筋組織に血液を送る役割を持っています。
狭心症は、冠動脈が狭くなったり閉塞したりすることで一時的に心筋が酸素不足になり、胸の痛みや胸部の圧迫感を引き起こす疾患です。
狭心症の診断には血液検査、心電図、カテーテル検査などさまざまな検査が行われます。医療従事者はこれらの検査をどのように活用し、診断や利用に生かしているのでしょうか。
ここでは気になる胸部症状がある方、精密検査を検討している方、あるいは近々人間ドックを受診する予定のある方などに向け、狭心症の検査方法について詳しく解説していきます。
目次
血液検査

狭心症の患者さんにおいて血液検査は、心筋ダメージの有無やその重症度などを評価するために行われます。
通常では、狭心症は心筋梗塞と違って心筋の酸素不足が短時間に限られているため、血液検査で顕著な異常所見を認めることはあまりありませんが、心筋虚血の有無などを確認するためには有用な検査といえます。
狭心症を血液検査だけですべて確実に診断することは不可能ですが、急性心筋梗塞の場合には血液検査において白血球やクレアチニンキナーゼ(略称:CK)などが上昇することが知られており、血液検査の結果によって心筋梗塞に進展しているかを判断することができます。
また、狭心症の背景には動脈硬化病変が潜んでいるケースが多いので、糖尿病や脂質異常症、腎臓疾患などの診断のサポートにも血液検査は有用であると考えられており、スクリーニング検査としても非常に広く普及しています。
運動負荷心電図検査
心電図検査は心臓の電気的な信号を身体に取り付けた電極によって感知し、電波波形として記録用紙に反映させる検査方法です。
通常では、心筋細胞が酸素不足に陥って虚血状態になるとST変化と呼ばれる心電図上の特徴的な波形所見が認められることが周知されており、狭心症をはじめとした冠動脈病変を診断する上で重要な手掛かりとなる検査のひとつと考えられます。
狭心症の中には、時に胸痛発作を自覚しているときにしか有意な異常波形が認められないことも経験されます。
したがって、特に安静時狭心症ではなく労作性狭心症が疑われる際には踏み台昇降などを実施して運動を行い、運動をする前後での心電図波形の変化を読み取ることができる運動負荷心電図検査が有用であると考えらえれています。
心エコー検査

心臓超音波検査、あるいは心エコー検査は心臓が動いているかどうか、あるいは心筋の収縮機能などを評価できる検査です。
この検査は、入院せずに外来レベルでも簡便に侵襲なく実践することが可能であるため、狭心症を発症したときのみならず発症後の経過中に心機能を観測する場合にも有用であると考えられます。
実際の手技では、患者さんの胸にプローベを当てて、心臓そのものの形状や働きを観察します。弁組織の石灰化変化や逆流性病変、心室内における血栓や腫瘤、心嚢液の貯留の有無など多くの情報を汲み取ることができます。
狭心症が重篤化して心筋虚血が進展した場合、心臓の部屋に穴があく、あるいは心臓の壁表面から出血を来しているか否かの判断も可能です。
ホルター心電図
狭心症患者さんの中でも日常生活において胸が痛むことがある、または夜間から早朝にかけて胸痛発作が自覚されやすい所見が認められる場合には、24時間継続して心電図を記録して検査することがあります。
ホルター心電図と呼ばれるこの検査は病院に入院することなく実施できる有効な検査手段であり、1日24時間分以上の心電図変化の記録を後に分析することができます。
本検査を受けることにより、夜中に引き起こされやすいと言われている狭心症の発作時における心電図変化やその他の不整脈の出現をチェックできるのみならず、不整脈自体の種類やその頻度などが客観視できるため、狭心症診断の手助けになる手法と考えられます。
胸部レントゲン検査
狭心症そのものを胸部レントゲン検査で確実に判明することはできませんが、心電図と同様に簡便で迅速に用意できる検査であると言えます。
特に心臓が拡張していないかどうか、あるいは肺の血液が滞留して肺血管拡張像などを認めないかを判定でき、胸部症状が仮に心臓疾患以外の肺病変や肋骨異常から由来している場合には、本検査を受けることが有用であると思われます。
心臓CT検査

近年では、特にComputed Tomography(略称:CT)自体の画像診断技術が飛躍的に成長しており、拍動している状態の心臓の働きをくまなく撮影することが可能になり、簡便に用いることができるスクリーニング検査としても広く普及しつつあります。
最新の造影剤を用いた心臓CT検査では、左右の冠動脈の状態を三次元構造として詳細に描出して捉えることができるのみならず、心臓の形状や、大動脈における動脈硬化や石灰化組織の有無、あるいは肺病変の有無なども併せて評価することができます。
心臓MRI検査
心臓MRI検査は体への負担が少ないことが特徴で、電磁力を利用した核磁気共鳴画像装置を用いて心臓に異常所見があるかどうかを診断できる優れた検査方法と言えます。
Magnetic Resonance Imaging(MRI)検査では、CT検査やX線検査のような放射線被ばくの心配がなく、身体に強い苦痛を伴うこともほとんどありません。
心臓MRI検査では、冠動脈の走行具合や血管病変の有無やその狭小程度、あるいは血栓の有無などをあわせて評価することができます。
ただし、心臓ペースメーカーを埋め込んでいる方、以前の手術で体内金属が留置されている方、人工内耳を装着されている方や妊婦さんなどは、基本的には造影剤を用いたMRI検査を受けることができないことを知っておきましょう。
血圧脈波検査
実際の医療機関における診療場面では、問診で狭心症の病気が疑われた患者さんに対しては、血圧脈波検査を行って心臓以外にも末梢血管などが障害されていないか詳細に評価していくことがあります。
狭心症が疑われるケースにおいて血圧脈波検査を実施することで、狭心症以外の動脈硬化由来の血管疾患などを合併していないかを確認できます。
本検査では、ベッドに横になり、両手足に血圧計を装着して左右の血圧をそれぞれ測定し、上肢の血圧と足首の血圧の比率を計算することで末梢血管の閉塞度合いを評価することになります。
ただし、この検査は透析シャントのある方には実施できないことを知っておきましょう。
心臓カテーテル検査

狭心症をより確実に病状診断する場合には、一般的には心臓カテーテル検査で冠動脈の病変部を確認する必要があると言われています。
この検査は冠動脈の入り口まで直接的にカテーテルデバイスを挿入して、正確に冠動脈の狭窄程度を診断することができます。ただし、他の検査に比べて侵襲が高く、患者さんに大きな負担がかかることが従来から改善課題と認識されています。
実際の手技では、足の付け根にある大腿動脈や腕の血管である橈骨動脈などから医療用の細い管であるワイヤーを挿入し、同部よりカテーテルを通過させて心臓まで至ったところで造影剤を流し込むことで冠動脈の病変部の状態を詳しく評価します。
冠攣縮性狭心症が疑われる人の場合には、冠動脈の攣縮を促進するアセチルコリンという薬剤をカテーテルから冠動脈内に注入し、実際に胸痛発作が生じるかどうかを確認するアセチルコリン負荷試験を実践することが可能です。
こんな自覚症状がある人は検査を

狭心症の検査が必要なのは、例えば次に挙げるような症状がある方です。
締め付けられるような胸の痛み
狭心症は、労作時に胸部中央から左側にかけて締め付けられるような痛みや圧迫感があり、数分で消失し、安静時や夜間、明け方の寝ている時に起こるようなタイプもあります。
これらの痛みがよりひどく、持続時間も長く、冷汗や呼吸困難などのその他の症状を認めた場合は心筋梗塞を疑います。
胸痛という症状をきたす疾患の中でも、狭心症による場合には特に生死に直結する可能性があるため、循環器内科など専門医療機関で心電図や採血、心臓カテーテル検査などを受けて、緊急対応が必要になることが多いです。
動悸・息切れ・冷や汗
動悸は、心臓の拍動が感じられる状態のことです。
心拍が速い頻脈、遅い徐脈、心拍を大きく・強く感じる、脈が飛ぶ・乱れるなどがあります。
脈が飛ぶ・乱れるタイプは不整脈の可能性があり、重大な発作を予防するために早めの循環器内科受診が必要です。脈が速くなる・遅くなるきっかけや時間、直前まで行っていたこと、他の症状の有無などを問診で確認して、適切に検査・診断していきます。
動悸にふらつきや息切れをともなう場合には心不全を起こしている可能性がありますので、早急に専門医療機関を受診して心臓超音波検査や心臓カテーテル検査など適切に診断を受けることが重要です。
また、動悸と共に冷や汗、失神などの症状を合併している場合は、狭心症や心筋梗塞が疑われるため、救急車を呼ぶなど緊急的な対応が必要になります。
放散痛
狭心症では、時に首や肩などにも広がるような痛み(放散痛)や上腹部の痛みなどとして現れることもあります。
心臓の病気になると現れる代表的な症状は胸の痛みですが、それ以外にも放散痛などを自覚することもあり、症状の現れ方は人それぞれです。
特に、放散痛の場合には、胸以外の場所で左肩、上腕、背中、のど、歯、みぞおちの部位などに重苦しさや圧迫感を感じて、やや広範囲に痛むのが特徴的です。
狭心症を含めて、心臓の病気を調べる方法は沢山あります。狭心症に対する代表的な検査は、まずは問診として、いつ、どんな場合に、どのような症状が現れたか確認します。
そして、心電図検査によって安静時における心臓の拍動状態を調べる、あるいは胸部レントゲン検査を実施して、心臓の大きさなどを評価します。
積極的に狭心症などの病気が疑われる場合は、更に詳しい検査が行われます。例えば、心臓超音波検査で心臓の画像を映し出して、異常が生じている場所を調べる、運動負荷試験を行って、運動時の心臓の動きを測定して心電図に記録する検査などが挙げられます。
それ以外にも、心筋シンチグラフィーを用いて、医薬品を使って心筋(心臓の筋肉)の状態を撮影して血流を調べる検査手段も考えられますし、心臓カテーテル検査を実際に行って、冠動脈の病変の有無を調べる検査方法もあります。
最近では、造影剤を使って心臓を輪切りにするように撮影して、心臓の血管の状態を詳しく調べることができる多列検出器コンピュータ断層撮影(MDCT)と呼ばれる検査方法もあります。
まとめ
狭心症という病気は、生活習慣やストレスなどが関与して突発的に胸部症状が発症する疾患です。心臓に関する関連リスクを総合的に調査するためには、定期的な検査受診が推奨されています。
これまで述べてきたように狭心症の検査にはさまざまな種類があります。これらを上手に組み合わせて活用することで狭心症の状態を多角的に捉えることが可能になります。
今回の情報が少しでも参考になれば幸いです。





