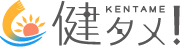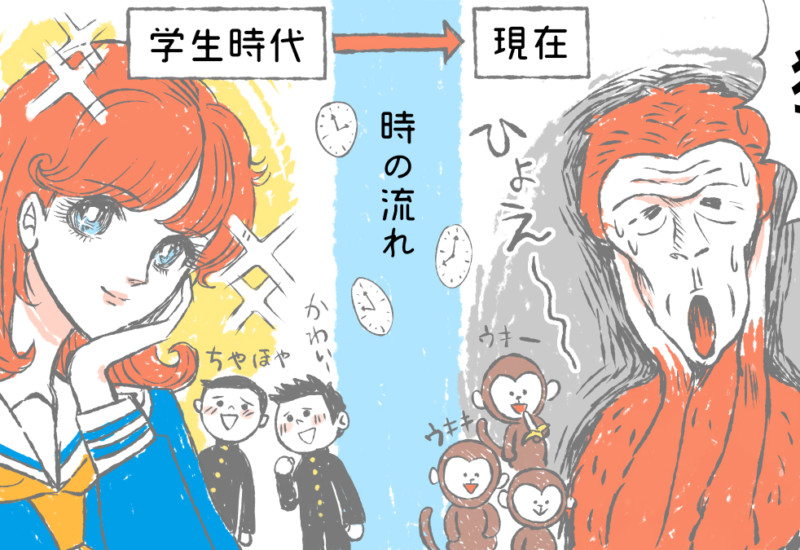大動脈瘤と大動脈解離の症状・予後・治療の違い

生死に関わることがある大動脈の疾患として、大動脈瘤と大動脈解離が知られています。この2つの病気にはどのような違いがあるのでしょうか?
ここでは大動脈瘤と大動脈解離を取り上げ、症状の特徴や予後、治療の違いについて詳しく見ていきましょう。
大動脈瘤と大動脈解離の違い

大動脈瘤と大動脈解離のそれぞれの概要と違いについて解説します。
大動脈瘤とは
大動脈は、心臓から全身に血液を送る働きを担っている血管のことであり、大動脈瘤は先天的な組織異常や後天的に発生する動脈硬化などによって大動脈領域にこぶ状のふくらみが形成される病気のことを指しています。
大動脈瘤は、患者さんが有意な自覚症状が乏しいままで経過することが多い疾患です。
ところが、いったん瘤が破裂した際には急激に大出血を起こして、死亡率が非常に高いために自覚症状の有無に関係なく、大動脈瘤が発見された時点で適切な治療が必要になります。
大動脈瘤を発症する原因として、ほとんどは生活習慣に関連した動脈硬化によって血管が老化現象を起こして脆弱になることが深く関与していますし、生まれつきの組織異常が関連しているケースもあります。
大動脈とは、心臓から送り出された血液を全身に供給する機能を有するために最も心臓からの血圧を直接的に受ける組織であり、万が一動脈硬化や組織異常などで血管が脆くなると高圧に耐えることができずに少しずつ血管が拡張して大動脈瘤が形成されてしまいます。
動脈硬化を引き起こす因子として糖尿病や高血圧、脂質異常症や喫煙習慣、日々のストレスなどが挙げられており、これらのリスク要素を持つ場合には大動脈瘤に罹患する危険性が上昇します。
それ以外にも、マルファン症候群など先天性の結合組織疾患でも大動脈瘤を発症することが多く見受けられますし、細菌感染や外傷から引き続いて二次的に大動脈瘤を形成することもあります。
大動脈解離とは
大動脈解離は、大動脈壁の内膜部分が裂けて、壁の中間層から剥がれる病気であり、ほとんどの場合には、高血圧などの基礎疾患によって動脈壁が劣化して脆くなることが直接的な原因と考えられています。
大動脈は全身で最も太い動脈組織であり、酸素を豊富に含有する血液成分を普段から全身に送り出していて、ほとんどの大動脈解離は胸部で発生すると言われています。
大動脈の壁の内膜組織がいったん裂けると、その裂け目に血液が勢いよく流れ込んで、外膜部から中間層が引き剥がされて血管が解離する結果、大動脈の壁の中に偽腔と呼ばれる空間が新たに形成されることに繋がります。
本疾患は女性より男性で約3倍多く認められ、人種別ではアフリカ系アメリカ人の黒人に多く見受けられ、発症者の約4分の3は、40~70歳の年齢層の方々です。
大動脈解離の最も一般的な原因は長期間の高血圧に伴う動脈壁の劣化ですが、それ以外にも遺伝性結合組織疾患であるマルファン症候群やエーラス・ダンロス症候群、あるいは動脈管開存症、胸部を強打したなどの外傷歴があれば罹患しやすいと考えられます。
時には、大動脈造影検査などでのカテーテルの挿入操作、あるいは心臓や血管の外科手術中に偶発的に合併して認められることがあります。
大動脈瘤と大動脈解離の違い
大動脈組織が障害されて形成される病気としては、動脈血管壁の弱くなった部分が膨張するタイプの大動脈瘤、そして動脈壁の血管内膜が剥離される解離性大動脈瘤があって、これらの病気は直接的に死に直結する危険性があります。
通常、脆弱になった血管内壁に高血圧などのリスク要素が加わって血管がこぶのようにふくらんだ状態になっているのが大動脈瘤である一方で、血管内壁の一部に亀裂が入って血管壁が剥がれて裂ける状態が大動脈解離という具合に区別されています。
両者ともに放置すると、血管が破裂して大出血を引き起こす命に直結する重大な病気であると認識されています。
大動脈瘤の症状と予後

大動脈瘤の症状としては、声がしゃがれる嗄声などが出現することも時に見受けられますが、発症者の多くは無症状であるためになかなか疾患が発見されずに経過し、大動脈瘤の破裂に伴う突然死などによって病気が初めて明らかになることも想定されます。
基本的には、大動脈瘤が発生している部位に応じて特徴的な症状が出現すると考えられています。
例えば、弓部大動脈の周囲に大動脈瘤が形成されると周囲の主要な組織が瘤によって圧迫されて、物の飲み込みにくさ(嚥下困難)やしゃがれ声などが認められるケースも存在します。
また、巨大な腹部大動脈瘤がある場合には、患者さん本人が腹部にドクドクと拍動するこぶを自覚する場合もありますし、破裂の危険性が切迫しているようなケースでは、動脈瘤の部位に沿って強い痛みを訴える患者さんもいます。
仮に大動脈瘤が破裂前に発見されて、適切な手術を実施して合併症もなく経過した場合には、術前とほぼ同様の日常生活を送ることができると考えられます。
大動脈瘤に基礎疾患となっている動脈硬化は全身病と考えられていますので、発症後も動脈硬化の悪化を予防することは重要であり、定期的な外来通院や高血圧などがあれば投薬治療、またCT検査などの画像診断による大動脈瘤の所見フォローも大切です。
大動脈解離の症状と予後

大動脈解離を発症した場合にはこれまでの人生で経験したことの無いぐらい耐えがたい激痛が急激に胸部や背部に認めることがあります。
大動脈解離が引き起こされると、患者さんは引き裂かれるような胸の痛みに伴って失神するケースも存在しますし、疼痛部位が大動脈に沿って進んでいくにつれて移動することも見受けられます。
大動脈の解離所見が大動脈に沿って進展すると、大動脈から枝分かれした別の動脈血管が閉塞して各臓器への血流が遮断され、例えば脳に血液を送る脳動脈が閉塞した場合には脳卒中という合併症を引き起こすことに繋がります。
それ以外にも、心筋に血液を送る冠動脈が閉塞した場合には急性心筋梗塞、腎臓に血液を送り込む腎動脈が閉塞した場合には急性腎不全、上腸間膜動脈が閉塞した際には強い腹痛症状と共に腸管壊死などを合併するリスクがあります。
また、解離部位が心臓に近ければ、漏れ出した血液が心嚢部分に貯留して心タンポナーデが発生することもありますし、心臓に最も近い部分である上行大動脈で解離が発症すると、心臓への血液の逆流を防いでいる大動脈弁の構造異常が認められるケースも想定されます。
大動脈弁の構造が異常を呈して、大動脈弁レベルで逆流所見が起こる結果として 心不全が悪化する可能性が懸念されます。
大動脈解離に対しては、通常安静にしたうえで血圧を下げる薬を投与する、そして根治的な外科手術を実施して裂けた患部を修復する、あるいはステントグラフトを挿入して裂け目を覆うような処置を実施することになります。
一般的に、大動脈解離を治療しない場合の死亡率は発症当初の2週間で高値となりますが、適切に治療して急性期を乗り越えた人の5年生存率はおよそ60%程度と考えられています。
大動脈瘤と大動脈解離の治療の違い

ここからは大動脈瘤と大動脈解離の治療の違いについて解説します。
大動脈瘤の治療
大動脈瘤は、患者さんが有意な自覚症状が乏しいままで経過することが多い疾患です。ところが、いったん瘤が破裂した際には急激に大出血を起こして、死亡率が非常に高いために自覚症状の有無に関係なく、大動脈瘤が発見された時点で専門医を受診して適切に治療を受ける必要があります。
大動脈瘤があまり大きくない場合には血圧コントロールなどで経過観察を行いますが、残念ながら薬物治療で大動脈瘤が小さくなることはなく、破裂の危険性が出てきた大動脈瘤に対しては治療を考慮する必要があります。
大動脈瘤の治療には大きく分けて、人工血管置換術とステントグラフト治療(ステントグラフト内挿術)の2つの方法があります。
人工血管置換術とは、胸やお腹を切開して大動脈瘤を切除した後、切除した部分を人工血管に置き換える治療法です。
ステントグラフト治療とは、カテーテルを使ってステントグラフト(金属性のバネ)を血管内に留置し、瘤の中への血液の流入を防ぎ破裂を予防する治療法です。カテーテルを使って治療ができるため、人工血管置換術に比べて患者さんにかかる身体的な負担が少ないという特徴があります。
ステントグラフトを用いた治療に際して、起こりうる合併症としては、動脈壁の損傷、塞栓症(脳梗塞や腎梗塞、腸管虚血、下肢虚血など)、ステントグラフトの閉塞や狭窄、ステントグラフトのずれなどが挙げられます。
実際に、どのような治療を行うかは、患者さんの全身状態や大動脈瘤の状態などを考慮したうえで決定します。
大動脈解離の治療
急性大動脈解離の治療は、スタンフォードA型とB型のタイプによって違ってきます。
上行大動脈に解離があるスタンフォードA型は、急死に至る心タンポナーデ、大動脈弁閉鎖不全症、心筋梗塞、急性心不全などの合併症を生じやすいため、緊急手術が必要です。
A型解離に対しては上行大動脈人工血管置換術、または上行大動脈と弓部人工血管置換術 を行います。
一方で、上行大動脈に解離がないスタンフォードB型は、大動脈の破裂している場合、または血液が十分に届かず臓器に障害が起こる場合は、胸部下行大動脈人工血管置換術の緊急手術を行います。
それ以外の場合は、まず血圧を下げて、解離進行や合併症が起こらないように治療管理します。
どの手術も危険性は10~30%前後であり、現代医学の中でも危険率の高い手術とされていましたが、近年手術手技の改良や人工血管の改良、体外循環法の確立により成功率の向上が報告されています。
また、解離による血流障害の合併症に対しては、開窓術などの手術を行います。
大動脈解離の予後は患者さんに対して慎重な姿勢が必要です。
臓器不全や破裂を起こす危険性の高い血管の手術で、一部を人工血管に置き換えても、それ以外の血管の多くは解離したまま残っています。また、解離を起こしやすい体質もそのままですし、解離を起こしやすい生活習慣もすぐには変えられません 。
そのため、解離が拡大し破裂しないように、日々の血圧の管理や病院での定期的な経過観察が必須となります。
急性期を乗り切っても楽観視するのは禁物ですし、残存している解離が拡張傾向にある場合には、再発症する前に治療を受けることが大切です。
まとめ
これまで、大動脈瘤と大動脈解離の症状と予後、両者の主な違いなどを中心に解説してきました。
血管がこぶのように膨張する大動脈瘤や血管壁が裂けて二層構造になってしまう大動脈解離を急激に発症した場合には、強い胸部症状を自覚することがあって、迅速な外科手術によって大動脈を修復する治療が必要になります。
また、発症に伴って起こり得る新たな解離所見の発生や大動脈弁からの逆流所見などの合併症の有無を評価するために、厳密な降圧治療や定期的な経過観察を継続することが重要です。
今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。