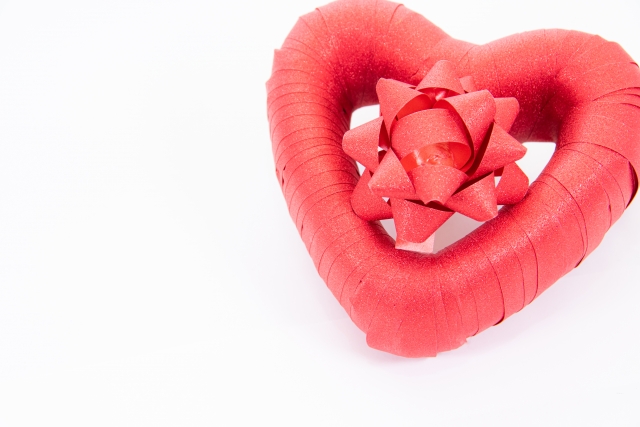胃もたれの原因とストレス性の胃もたれの改善方法

脂っこい食べ物を食べ過ぎたり、飲酒し過ぎたりしたとき、あるいは日々のストレスによって、胃もたれ症状を経験したことがある人も多くいらっしゃるでしょう。
また慢性的なストレスによって、胃の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れると、食べ物を消化して小腸に送り出す機能が低下し、胃もたれの症状が現れることがあります。ここでは胃もたれの原因と改善方法を紹介します。
目次
ストレス性の胃もたれの特徴

食後や食間に胃が重く感じる胃もたれは、暴飲暴食、加齢やストレスなどが影響して、胃の運動や消化機能が低下することにより引き起こされやすくなります。
胃の働きは、自律神経によってコントロールされていて、長期間のストレスによって自律神経のバランスが乱れると、食べ物を消化する準備をして小腸に送り出す胃の役割が低下することにつながります。
通常、食べ物が何らかの影響により消化が遅くなって、胃に食べ物が残留し続ける状態になると胃もたれなど不快な症状が出現しますし、胃もたれの感じ方も、人によってさまざまです。
ケースバイケースですが、胃もたれの症状としては、胃がずっしりする、常に腹部が苦しい、消化不良を起こして胃が張っている、長期間に渡って吐き気を催す、などが挙げられます。
胃もたれのその他の原因

胃もたれの原因としては、ストレス以外にも次のものが挙げられます。
加齢の影響
胃には、ぜん動運動によって、一定の時間をかけて食べ物を消化しやすい状態に変え、小腸に送り出す働きがありますが、加齢の影響で胃の働きが低下すると、食べ物の消化に時間がかかるようになり、胃に長くとどまることになるため、胃もたれが起こりやすくなります。
また、高齢になると胃の粘膜を守る血流が低下するために、胃に全般的な不調が起こりやすくなります。
暴飲暴食
食べ物には、ごはんやパンなどの炭水化物のように、比較的消化しやすいものと、揚げ物や焼肉などの脂っこい食事のように消化しにくいものがあります。
油物などを食べ過ぎると、食べ物が胃にとどまる時間が長くなるために、胃への負担も大きくなり、胃もたれが起こりやすくなります。
また、不規則な時間に食事をする、就寝の直前に食事をするなどは胃に負担をかけて、胃もたれ症状につながります。
過度の飲酒
体内に入ったアルコールの約20%は胃、残りの約80%は小腸で吸収されて、肝臓で代謝されますが、過剰に飲酒してアルコールを代謝しきれないと、アセトアルデヒドという物質が残り、胃もたれ症状につながります。
胃腸の病気
胃もたれは幅広い消化器疾患によっても生じやすい症状であり、特に胃もたれ症状を引き起こしやすい胃腸の病気としては、慢性胃炎、胃潰瘍、機能性ディスペプシア、胃がんなどが挙げられます。
胃もたれをきたす疾患のなかで、特に注意が必要なのは胃がんです。
胃がんは早期の自覚症状がほとんど現れず、進行しても軽い症状しか起こらないことがあり、定期的な胃カメラ検査により早期発見・早期治療につなげることが重要です。
また、ヘリコバクター・ピロリ菌に感染している場合、慢性胃炎から萎縮性胃炎に進行することがあり、萎縮性胃炎は胃がん発症のリスクが高い状態であるため、要注意です。
なお、ピロリ菌に感染している場合、除菌治療でピロリ菌を除去すれば胃炎の再発率を大幅に下げることができ、胃がん発症のリスクを軽減できます。
妊娠
妊娠すると、急激なホルモンや代謝の変化が起こることで、胃もたれや吐き気などの症状がみられることがあり、いわゆる「つわり」と呼ばれる状態です。
また、子宮が大きくなると、物理的に胃が圧迫されたり、働きが低下したりすることで、胃もたれなどの症状が起こりやすくなることも考えられます。
胃もたれの改善方法

胃もたれを改善するには、食生活の見直しとストレスとの上手な付き合い方が重要になります。
刺激の少ない胃に優しい食事
胃は食べた物を一定時間貯えて、消化しやすい形に変えて小腸に送り出しますが、一般的に食べ過ぎると胃に留まる時間が長くなって胃もたれの症状が起こりやすくなります。
食べ物には消化しやすいものと消化しにくいものがあって、焼肉や揚げ物、天ぷらなど脂っこい食事は、ご飯やパンなどの炭水化物に比べると消化に時間がかかりやすく、胃にかかる負担も大きくなるため、胃もたれが起こりやすくなります。
食生活の改善ポイントとしては、日頃から食べ過ぎずに腹八分目でおさえる、就寝の直前3時間ほど前には食事を完了する、脂っこいものや糖質の高いものを控えて刺激の少ない胃に優しい食事を心がける、食物繊維を意識的に多く摂取するなどが挙げられます。
アルコールやたばこを控える
通常であれば、アルコールの約20%は胃で吸収されて、残りの80%ほどが小腸から体内に吸収されます。しかし、アルコールを飲み過ぎると胃酸から胃壁を守っている粘膜の働きが破綻して、胃粘膜の血流障害が起きて胃もたれ症状を起こすことがあります。
また、体内に吸収されたアルコール成分は主に肝臓で代謝されますが、代謝しきれずにアセトアルデヒドという物質が過剰に残ると、その毒性によって二日酔いや胃もたれの症状が出現しやすくなります。
胃粘膜は胃液によって刺激を与えられないように、粘液によって保護されていて、胃粘膜の正常な働きは、血流によって栄養や酸素が供給されることで維持されています。
また、タバコは通常、全身の血管を収縮させて胃の血行を悪くするので、胃もたれ症状を改善したい場合には、禁煙することが重要です。
喫煙者は非喫煙者と比較して、胃潰瘍にかかりやすく、喫煙本数が多いほど死亡率が高いという調査報告もあります。
禁煙行為そのものがストレスになって胃に悪いという方の場合には、ニコチンのできるだけ少ないタバコを吸う、あるいは特殊フィルターを使用して少しでもタバコの本数を減らすようにしましょう。
ストレッチや呼吸法などでリラックスする

ストレスは自律神経のバランスを崩す原因になりますし、自律神経のバランスがいったん崩れると、胃の働きが低下してしまい、胃液の分泌量が減って食べ物を順調に消化できなくなります。
食べ物を胃から大腸へ送り出す蠕動運動が弱くなって食べ物が胃に残留することで、胃もたれを感じることになりますので、なるべくストレスを解消して生活習慣を改善することがポイントです。
ストレッチや有効な呼吸法など適度な運動を行い、睡眠時間を確保して、入浴時に湯船にしっかりと浸かるなど体温低下を防止することが重要です。
定期的に運動を実践することは、胃腸の働きの活性化に効果的と考えられていますので、普段から階段を使う、一駅分徒歩で動くなど日々の生活のなかに少しでも運動習慣を取り入れましょう。
趣味や習い事など好きなことに没頭する
極度の緊張が起きると、交感神経が刺激されるので胃粘膜の血管が収縮する結果、血液の流れが悪くなって胃粘膜への栄養供給が止まり、胃の粘膜の修復機能が低下し、胃の粘膜を保護する粘液の分泌量が減少して胃もたれを感じやすくなります。
ストレスを感じると胃内で胃酸などの攻撃因子と胃粘液などの防御因子の分泌バランスが崩れてしまい、胃粘膜への刺激が強くなり胃もたれなどの不快症状が起きるので、普段から自分の趣味や習い事など好きなことに没頭することもストレス対策になります。
気分転換を図ることで、嫌な気持ちを楽しい気分に切り替えて、嫌なことやストレスが溜まった場合に別方向へ意識を向けることで、心に余裕ができて胃のダメージも少なくなって胃もたれ症状が改善する効果が期待できます。
漢方薬を活用する

胃薬には、生薬や漢方成分を配合している胃腸薬が多くありますので、胃もたれがひどくなった際には、自分の状態に合わせて漢方薬を選択することも有用です。
例えば、半夏瀉心湯(ハンゲシャシントウ)という漢方薬は、ストレスで胃が痛くなった場合に用いる漢方薬であり、主に体力は中程度、食欲がなく、吐き気や下痢などの症状を有する場合に適しています。
胃の貯留機能を改善させる漢方薬としては六君子湯(リックンシトウ)が挙げられ、この漢方薬には排出機能を高めて、胃の血流をよくして胃粘膜を保護する作用や、気分をすっきり向上させる抗ストレス効果もあると言われています。
まとめ
これまで、ストレス性の胃もたれの特徴と改善方法などを中心に解説してきました。
胃のぜん動運動は、自律神経によって制御されていますが、普段の食生活で食べ過ぎや飲み過ぎ、さらには加齢やストレスなど胃の働きを低下させる要因が重なると、胃のぜん動運動が低下して食べ物が長く胃の中に停留して胃もたれ症状が出現します。
喫煙や過剰なアルコール摂取は避け、刺激物を控えた胃に優しい食事メニューを選びましょう。
また、日々のストレスをなるべく発散できるように、自分なりに趣味や習い事に没頭することによって胃もたれ症状が緩和される見込みもあります。
胃もたれ症状を自覚する際には、胃粘膜を保護して胃酸の働きを抑える胃薬や漢方薬などの服用を試すのも良いでしょう。
症状がいっこうに改善しない場合は、症状を軽視せずに消化器内科など専門医療機関を受診することをおすすめします。
今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。