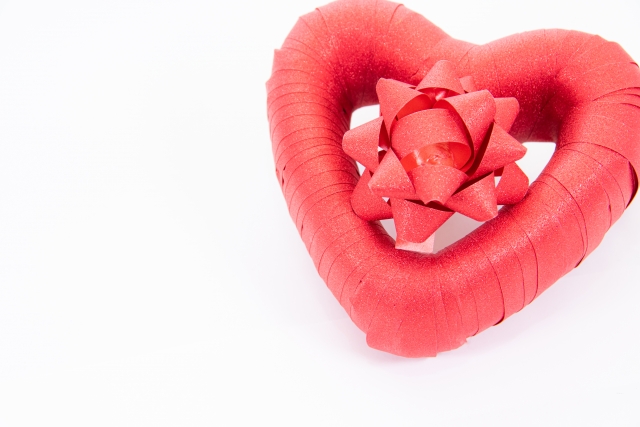喉の渇きの原因になる病気…尿崩症の症状と診断方法

尿崩症は腎臓の反応が悪くなるために起こる難病であり、尿の量が増加し、水分が失われるなどの影響が出ます。ここでは尿崩症の症状の特徴や診断方法について解説します。
尿崩症の症状

尿崩症は腎臓でできた尿をじゅうぶんに濃縮できず、大量の尿が出てしまう病気です。
尿崩症の主な症状には、尿量の増加、のどの渇き、大量の水分摂取が挙げられます。
抗利尿ホルモンが分泌されない場合や、腎臓が正しく機能しておらず正常に尿の量が調節できていないため、尿の量が通常よりも非常に増えます。
また、大量の水分が体内から失われてしまうために、のどの渇きを感じるようになります。
その結果、大量の水分を摂取するという症状も発症します。
多い場合は1日10L程の量を摂取して、10Lの尿を出すこともあるため、脱水症状や夜間でも尿意で目が覚める場合もあります。
尿崩症を発症すると、多尿の結果として、脱水となり、強い喉の渇きを感じたり、失った水分を補うために多量の水分摂取につながったりします。
また、体内から尿と共に水分がどんどん排出されていくため、じゅうぶんな水分を補わないと脱水や電解質異常に陥りやすく、血圧低下などを引き起こすこともあります。
尿崩症のセルフチェック
尿崩症のセルフチェック方法としては、次のような症状に心当たりがあるかを確認しましょう。
・尿が我慢できないと感じて、急いでトイレに行くことがある
・尿の回数が増加した
・尿のために夜起きてしまい困る
・体がだるい
・認知症と診断されたことがある
もしも、これらの症状に悩んでいるということであれば、念のため医療機関を受診して相談しましょう。
抗利尿ホルモン(ADH)とは

通常、尿は抗利尿ホルモンによって調節されながら、腎臓によってじゅうぶんに濃縮が行われて体外へ排出されています。
抗利尿ホルモン(ADH)は尿の量を少なくする作用を持つホルモンです。
血液中のこのホルモンが少なくなると尿の量は増加し、多くなると尿の量は減少します。
これにより体内の水分量を調節しているのですが、尿崩症にかかると抗利尿ホルモンが正しく作用せず、希釈された大量の尿が出てしまいます。
抗利尿ホルモン(ADH)は脳の下垂体と呼ばれる部位から分泌されるホルモンですが、欠乏する代表的な原因としては、頭部外傷、腫瘍、脳梗塞、脳出血、脳炎、髄膜炎などによる視床下部から下垂体の損傷が考えられます。
尿崩症の種類

尿崩症は、水を体内に保つ作用を持つ抗利尿ホルモンの分泌が欠乏することによる中枢性尿崩症と、抗利尿ホルモンの効きが低下することによって尿量が増える腎性尿崩症の2つのタイプに分けられます。
中枢性尿崩症
健康状態においては、抗利尿ホルモンは脳の一部である視床下部で生成され、下垂体へと移動・保存されます。
そして、水分が足りない状況になると、下垂体から抗利尿ホルモンが分泌されるのです。
分泌されたホルモンは血液によって腎臓に運ばれ、腎臓に働きかけることで尿を濃縮します。
尿によって体内の水分量を調節し、正常な水分量に保つのですが、この抗利尿ホルモンを生成・分泌するところから腎臓までの経路のどこかで異常を起こすと、尿を調節することができなくなり、尿崩症を引き起こします。
特に、中枢性尿崩症は抗利尿ホルモンの分泌が正しく行われなくなることで発症します。
通常、抗利尿ホルモンは視床下部や下垂体において分泌されますが、外傷や脳腫瘍の影響で、正常に分泌されなくなってしまうことで尿崩症が発症するのです。
遺伝的要因による発症が疑われるケースや原因がはっきり分からないケース(特発性)もあり、特発性中枢性尿崩症では自己免疫的な機序の関与が想定されています。
腎性尿崩症
腎性尿崩症は、腎臓が抗利尿ホルモンに対して適切に反応しなくなったために発症するケースです。
この場合は、抗利尿ホルモンは正常に分泌されながらも腎臓が反応しないために尿崩症を発症します。
腎性尿崩症では、抗利尿ホルモン(ADH)は正常に分泌されているものの、尿を生成する腎臓の機能に異常があるため水分が再吸収されず過剰に排出されます。
主な原因は、遺伝子の異常によるものでX連鎖性潜性遺伝形式を示すタイプが先天性の腎性尿崩症の約90%を占めており、電解質異常(高カルシウム血症・低カリウム血症)も後天性の腎性尿崩症を引き起こす大きな要素です。
一部の薬剤は抗利尿ホルモン(ADH)の腎臓へのはたらきかけを減弱させる作用を持つものもあり、副作用として腎性尿崩症を発症することが知られています。特にリチウムは長期的に内服することで高頻度に腎性尿崩症を引き起こします。
腎性尿崩症は、抗利尿ホルモンに対する腎臓の反応性が低下するために尿を濃縮することができず、希釈された尿が出て、尿の量が増加します。
尿量が増加して水分が失われるため、のどが渇き、大量の水分を摂取するようになります。
腎性尿崩症は 遺伝子の変異による先天性、あるいはその他の原因で発症する後天性に分類することができます。
尿崩症の診断方法

尿崩症の診断には、主に水制限試験を用いて行います。
水制限試験とは、水分摂取を禁止して行う試験です。
12時間水分摂取を行わず、定期的に尿の量・血液中の電解質濃度・体重などの変化を測定します。
そして、12時間経過後は抗利尿ホルモンを投与し、それに対しての体の反応も測定するのです。
ホルモン投与後に排尿の増加が止まり、尿が濃く・血圧上昇・心拍数が正常に近い場合は中枢性尿崩症と診断されます。
一方、投与後も排尿増加が続き、尿は薄く・血圧と心拍数の変化がない場合は腎性尿崩症です。
尿崩症の検査としては、尿検査、血液検査、画像検査などが挙げられます。
尿検査によって、尿が薄くなっていないかを確認します。
血液検査では、血中のナトリウムや血漿浸透圧を測定し、体内の水分がどの程度失われているかを測定します。
尿崩症では必要な水分がどんどん排出されていくため、血液中のナトリウムなどの濃度が高くなります。
画像検査は、MRIによる検査であり、抗利尿ホルモンを生成・分泌する部位に異常がないかを確認して、抗利尿ホルモンの存在を示す信号が正常に存在するかも評価します。
他にもある喉が渇きやすい病気

喉が渇きやすい病気は尿崩症の他にもあります。代表的なものを確認しましょう。
糖尿病
糖尿病は1型糖尿病と2型糖尿病に分類され、その中でも2型糖尿病は生活習慣に強く関連した頻度が高いタイプです。
糖尿病に罹患すると、慢性的に高血糖が続くために、喉が渇きやすくなり、尿量増加、体重減少などの身体のサインが現れる場合もありますが、顕著な自覚症状が認められないケースもあります。
特に、1型糖尿病のケースではインスリンを分泌する膵臓の細胞が破壊されることで急激に血糖値が上昇するため、喉の渇き、頻尿、多飲、足のしびれなど神経障害、体重減少、疲労感などが突如として出現することもあります。
また、血糖値が高い状態が続くと血液中に多量に存在するブドウ糖が血管の壁を傷つけることで目や腎臓、神経領域にも十分な血液が供給されにくくなることで網膜症や腎機能傷害、そして末梢神経障害などいわゆる糖尿病の三大合併症を引き起こすことが知られています。
甲状腺機能亢進症
甲状腺機能亢進症は、甲状腺の過活動によって甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気です。
主な症状としては、のどの渇き、甲状腺の腫れ、大量の発汗、体のほてり、食欲亢進、体重の減少、手の震え、動悸、息切れ、疲れやすいなどが挙げられます。
これらの症状を引き起こす理由は、甲状腺ホルモンが交感神経への刺激を強くして、体の熱産生を活発にさせるためであると考えられています。
シェーグレン症候群
シェーグレン症候群は、免疫のバランスが崩れることによって涙や唾液を産生する涙腺・唾液腺などの臓器を攻撃し、眼乾燥(ドライアイ)や口腔乾燥(ドライマウス)をきたす病気のことです。
自己免疫性疾患の一種であり、涙腺や唾液腺だけでなく全身の関節、肺、皮膚、消化管、腎臓などさまざまな部位にダメージが及ぶこともあります。
シェーグレン症候群を発症すると目や口の乾燥が目立ち、のどの渇きを感じるようになります。
シェーグレン症候群の一部の人には、目や口の乾燥に伴うのどの渇き以外にも、腎臓、肺、皮膚などにも病変が現れたり、まれに悪性リンパ腫の合併が見られることもあります。
まとめ
これまで、喉の渇きや多尿の原因になる尿崩症の症状の特徴と診断方法などを中心に解説してきました。
尿崩症を発症すると多尿(成人の場合1日3L以上)をきたし、強い喉の渇きを自覚するようになります。
また、体内から水分が失われるため、じゅうぶんな水分補給を行わないと脱水に陥りやすく、低血圧やショック状態によりめまい、動悸などの症状を引き起こすことがあります。
尿量が増えたとき、のどの渇きをいつまでも感じるとき、沢山の水分を摂取するようになったときなど、尿崩症の疑いがある場合は、まずは一般内科を受診しましょう。
一般内科を受診した結果、中枢性尿崩症の可能性がある場合には内分泌科、腎性尿崩症の場合には腎臓内科など専門医療機関で検査や治療を継続するのが一般的です。
今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。