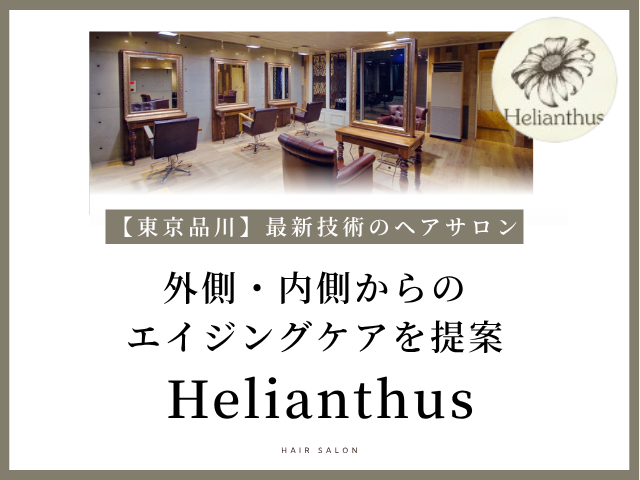食道がんに初期症状はある?リスク要因をチェック

食道がんとは、解剖学的に喉と胃をつなぐ場所にある約25cm程度の食道部位にできる悪性腫瘍(がん)のことです。食道がんになりやすい人にはいくつもの傾向が見られます。ここでは食道がんのリスク要因や初期症状について解説します。
目次
食道の構造と働き

いわゆる「食道」と呼ばれる内臓は、口から食べた物を胃に運ぶ働きを持つ管状の臓器です。
私たちの口から食べ物が入ってきた際には、食道壁が自然と動かされて食べ物が胃に送られる仕組みになっています。
食道は体の中心部にあり、その周囲には心臓や大動脈、肺といった重要な臓器に囲まれています。
食道の構造として、粘膜、粘膜下層、固有筋層、外膜の4つの層から構成されています。
食道は食べ物が通りやすいようになめらかな粘膜で覆われております。
これらの粘膜が粘液を分泌しており、粘膜の下にある粘膜下層は血管やリンパ管が豊富な層であり、さらに粘膜下層の下に位置する固有筋層は食道の中心にあり、食道を動かしている筋肉の役割を担っています。
食道がんとは

食道がんは必ず表面(粘膜)に発生し、徐々に深部へ浸潤するように進行します。
そして、本疾患は癌細胞の種類により主に扁平上皮がんと腺がんに分類されます。
食道の長さは25㎝ほどであるとされており、部位別に頸部、胸部、腹部に分けられます。
通常では、扁平上皮がんは上部に多く、腺がんは下部に多く見られる特徴があります。
統計学的に、女性よりも男性に多いがんとして知られていて、初期段階では食道の表面から発症し始め、がんが進行すると深い層まで侵されることになります。
そのうち、粘膜内だけにあるものを「早期食道がん」と呼び、粘膜下層まで至るものを「表在食道がん」、それ以上に深い層まで進行しているものを「進行食道がん」と分類して呼んでいます。
特に、日本人の場合には、約半数の割合で食道の中央付近から発症すると言われており、場合によっては同時に複数のがんができることもあり得ます。
喫煙や飲酒は全体的にがんの発症に関係があるといわれていますが、食道癌に限っては他種の癌疾患よりもこれらのリスク因子が発症に大きく関係していると考えられています。
食道がんは進行が早く、リンパ節への転移が特に多く起こりますし、食道の上部は気管と背骨の間にあり、下部においては心臓や大動脈、肺に囲まれているため他臓器に浸潤しやすく、進行すれば手術が難しいことも特徴的です。
食道がんは早期発見して早期的に治療ができれば、比較的良好な予後が期待できます。
食道がんのリスク要因をチェック

食道がんの代表的なリスク要因をチェックしておきましょう。
飲酒の習慣がある
毎日3合の飲酒を続けた際には、食道がん以外のがんの場合は発症リスクが約1.6~1.7倍程度であるのに対して、食道がんでは同量の飲酒によって約5倍もリスクが上がるといわれていますので、毎日の生活の中で出来る限り節酒するように心がけましょう。
飲酒をした際に顔が赤くなる
また、遺伝的な体質として飲酒をした際に顔が赤くなる方は本疾患になりやすいというデータがあり、こういった体質の方々は飲酒しなければ食道がんを発症する危険性は増えませんので、自分の体質をよく理解してできるだけ飲む量を減らすことが重要です。
喫煙習慣がある
そして、喫煙行為そのものが食道がんの発症リスクを高めることが判明しているため、可能なかぎり禁煙に努めるようにしてください。
ここからは食道がんの症状や、食道がんになりやすい人の特徴について、さらに詳しく見ていきましょう。
初期症状はない?食道がんの症状

食道がんの初期段階では、あまり自覚症状を持たないケースがほとんどです。
癌病変そのものが進行すると、次にあげるような症状が現れることがあります。
食事の際の胸のつかえ
食道は咽頭(のど)から胃につながっている管状の臓器です。胃や大腸などと同じく食道にもがんができることがあり、食道にできる悪性腫瘍が食道がんです。
食道がんの症状の一つとして、食事の際の胸のつかえを含めて、嚥下障害が挙げられます。
嚥下障害とは、食べ物を飲み込む際にのどや食道に食べ物がつっかえたり、詰まったりする感覚がありうまく飲み込めない状態です。
食道がんによって食道が塞がれてしまうため、食べ物が通れなくなることで起こります。
食道がんがまだ小さい段階では起こりにくく、主に食道がんが進行している場合にみられる症状です。
胸や背中の痛み
口から入った食べ物が食道を通っていく際に、胸の奥がちくちくする、あるいは熱いものを飲み込むとしみることがあり、この症状は食道がんの初期段階にみられる症状の一つです。
食道がんが進行すると、「食べ物を飲み込むときに、胸がチクチクと痛む」、「熱いものを飲むときにしみる」、「食べ物がつかえる感じがして、うまく飲み込めない」などといった症状が出てくるようになります。
また、がん細胞が周りの臓器やリンパ節にまで広がって波及してしまうと、胸の奥や背中に痛みを感じたり、痰に血が混じったりするようになります。
食道がんが食道の組織から波及して、周囲に存在している肺や脊椎、大動脈を圧迫すると、胸や背中の痛みを感じるようになります。
この症状は、心臓や肺の病気が原因で現れる場合もありますが、食道がんでもみられる症状であるため、心臓や肺の検査だけではなく食道も検査することが大切です。
声がかすれる
食道がんが大きくなり、気管や気管支を圧迫したり、気管や気管支などに浸潤したりすると、その刺激によって咳が出ることがありますし、声帯を調節している神経に浸潤すると声がかすれることがあります。
食道がんは反回神経という声帯を動かす神経のまわりにリンパ節転移が起こることが多く、最初に出る症状が嗄声であることも多いです。嗄声とは、声がかすれることです。
食道の近くには声を調整する反回神経があり、食道がんが周りのリンパ節に転移すると、反回神経は麻痺するため脳からの刺激を伝えられなくなります。その結果、声を出す声帯が機能しなくなって声がかすれたり、声が出にくくなったりします。
体重減少
食道がんが大きくなると食道の内側が狭くなり、食べ物がつかえやすくなるため、やわらかい食べ物しか通らなくなり、食事量が減って、栄養が不足するため体重が減少していきます。
ひとつの目安として、およそ3か月の期間で5~6kg程度の体重が減少した場合は、食道がんに注意する必要があります。
心配であれば、消化器内科など専門医療機関を受診して、上部内視鏡検査などを含めて、精密検査を受けることをおすすめします。
食道がんになりやすい人の特徴

食道がんになりやすい人の特徴としては次のものが挙げられます。
お酒を飲むと顔が赤くなる人
飲酒は食道がんの発症につながる大きな原因のひとつです。
アルコールが体内で代謝されてできるアセトアルデヒドという発がん性物質が食道がんのリスクになることが知られています。
さらに、このアセトアルデヒドをさらに分解するための酵素の働きが弱く、お酒を飲むと顔が赤くなる人は食道がんになりやすいと言われています。
特に、もともとはアルコールで酔いやすい体質であったにもかかわらず、慣れてきて飲酒量が増えてしまうと、食道がんの危険性は高まると考えられています。
たばこを吸う人
たばこの煙は発がん性物質をたくさん含んでいることから、喫煙者は必然的に食道癌を発症しやすくなります。
たばこの煙を周囲の人が吸い込んでしまう受動喫煙も食道癌を罹患させる確率に影響を与えることが分かっています。
喫煙習慣がある人や受動喫煙の機会が多い人は食道がんを発症する危険性が高まることを知っておきましょう。
バレット食道と診断された人
逆流性食道炎に合併してバレット食道と診断された場合には、逆流した胃酸が慢性的に食道を刺激するため、食道がんの発症リスクを高めると言われています。
バレット食道は、食道と胃上部の接合部に発生する粘膜組織の変化で食道がんの危険因子であり、食道がんの前がん病変とも考えられています。
食道にできるがん(食道がん)については、日本では扁平上皮がんと呼ばれるお酒やたばこが発症に関与するものが多くを占めていましたが、近年になって食道と胃の境界部から発生するバレット食道がんとよばれる腺がんが徐々に増加しています。
バレット食道がんとは、食道粘膜にできたバレット粘膜から発生するがんです。
バレット食道がんが引き起こされる主な原因は逆流性食道炎などによる慢性的に継続する炎症所見であり、これまで欧米で多く発症する病気でしたが、食生活の変化などによって日本人においても段々と罹患率が上昇しています。
まとめ
これまで、食道がんになりやすい人の特徴、その初期症状とチェックポイントなどを中心に解説してきました。
食道がんでは男女罹患率、死亡率に大きく差があり、男性は女性の5倍以上だと報告されています。食道がんの発生には日常生活における飲酒や喫煙行動が大きく関係していると考えられます。
心配な方は消化器内科など専門医療機関を受診して相談しましょう。
今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。