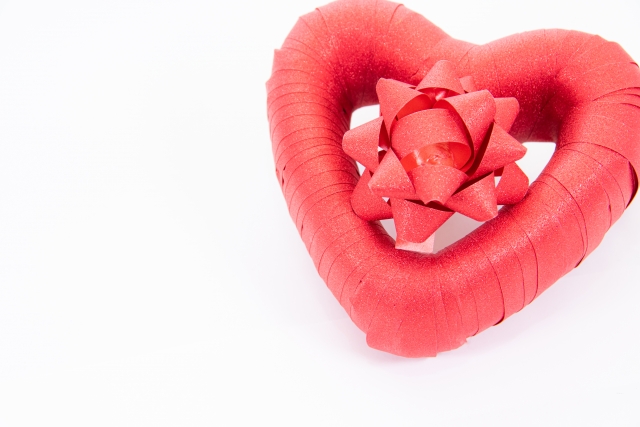横腹が痛くなる原因と関連する病気

運動をしたり食事をしたりすると横腹が痛くなることがあります。横腹の痛みは正常な生理的な反応のこともあれば、何らかの病気を原因としていることもあります。ここでは横腹が痛くなるメカニズムや関連する病気について見ていきましょう。
目次
日常生活で横腹が痛くなる理由

日常生活で横腹が痛くなる理由はいくつも考えられます。代表的なものを確認しておきましょう。
運動時の横腹の痛み
運動時の脇腹の痛みは、多くの人が経験したことのある不快なものであり、痛みが激しい場合には本当に運動することが困難になり立ち止まってしまうほどです。
走っているときに起こる、肋骨下や腹腔全体の差し込むような痛みの原因はさまざまありますが、そのなかでも特に「横隔膜とその付近の筋肉や内臓への血流不足、酸素の供給不足」が主たる原因です。
痛む部位は肝臓が位置する右側が圧倒的に多いようですが、肝臓自身に問題があるのではなく肝臓がぶら下がっている横隔膜の攣縮などが不規則に現れて、比較的短時間で収束する痛みであると考えられています。
横隔膜は息を吸ったり吐いたりする度に上下に動いていますが、ランニングなど運動するときには、体内の臓器も身体の動きに伴って揺さぶられることになります。
それによって、横隔膜や呼吸に関係する筋肉が痙攣し、脇腹が痛くなるというのが、運動時の横腹の痛みが引き起こされるメカニズムと考えられています。
食後の横腹の痛み
食後にみぞおちや横腹が痛むというときには、機能性ディスペプシアなどの病気が疑われます。
機能性ディスペプシアに見られるその他の症状としては、胃もたれ、あるいは食事の途中で満腹を感じて充分量を食べられない早期膨満感などが挙げられます。
また、脂っこいものやアルコールを摂取したあとに横腹の痛みなど腹痛が生じるときには、慢性膵炎などの病気が疑われます。
慢性膵炎に認められるその他の症状としては、背中の痛み、下痢、体重減少などが挙げられます。
毎食後に腹痛が起こるような場合には、食生活の乱れ、過労やストレスなど以外にも、ピロリ菌感染症といった病気も疑われます。
横腹が痛いときに考えられる病気や異常

何らかの病気が原因で横腹が痛くなることがあります。代表的な疾患を見てみましょう。
虫垂炎
虫垂は大腸の一番奥の盲腸にくっついている細長い袋状の臓器で、腹部の右下に位置しています。虫垂炎は、細菌感染などが原因で炎症が起きている状態で、痛みや発熱を伴います。
成人だけでなく子どもでも起こりますが、半数は典型的な症状を示さないことから、比較的判断しにくい病気です。
虫垂炎の症状の特徴
虫垂炎は、右下腹部に痛みがある場合や、最初にお腹の真ん中に痛みを感じ、そこから痛みの場所が下部に移動してさらに痛みを感じるという場合がありますし、病状が悪化すれば、腹部全体に炎症が広がって、いわゆる腹膜炎の状態になります。
人によっては、虫垂炎では我慢できないほどの激痛が腹部に生じることもありますし、吐き気や嘔吐、発熱を伴うこともあるのが特徴です。
さらに、症状が進むと腹膜炎や穿孔を起こし、手遅れの場合は、敗血症や播種性血管内凝固症候群などを起こして命を落とすこともあります。
虫垂炎は、初期の段階では、みぞおち辺りに感じる痛みが、時間の経過とともに虫垂がある右下腹部に移動していく場合があります。
右下腹部の痛みによって虫垂炎かもしれないと疑うことも少なくありませんが、痛みの場所は必ずしも決まっているわけではなく、人によって違うため、虫垂炎であるという判断がつきにくいケースもあります。
虫垂炎の原因
虫垂炎の原因の多くは、細菌やウイルスが虫垂に感染することで炎症を起こすのが原因であるとされていますし、糞石(硬い便のかたまり)が虫垂に詰まることで虫垂炎が発症する場合もあります。
一般的に、日常生活の不摂生により、体力が消耗していくと菌やウイルスに感染しやすくなりますし、便秘や胃腸炎、風邪、ストレス、日常生活の不摂生も、虫垂炎の発症原因の一つとして考えられるでしょう。
また、便秘などで生じる糞石が、虫垂に詰まることで閉塞し、虫垂炎が発症する場合があり、糞石の形成には、食物繊維の摂取が少ない食生活が関与しているといわれています。
加齢や体質によって免疫力の低下が見られると、虫垂炎の発症につながることがありますし、免疫力が低いと炎症を起こしやすい傾向があります。
虫垂炎の発症から数日間無治療でいると症状が進み、場合によっては重症化していき、腹膜炎や穿孔を起こし、手遅れの場合は命を落とすこともあるといわれています。
ですから、痛みを軽視せずに虫垂炎を疑ったらできるだけ早く受診してください。
憩室炎
憩室は消化管壁の一部が外側に突出し、嚢状(袋状の形)になった状態を指しています。食道、胃、十二指腸、小腸、大腸のいずれの部位にもできますが、大腸にできることがもっとも多い病気です。
特に、大腸憩室は、1個だけではなく複数個できる場合が多く、そのほとんどは後天的に出現して、大腸の壁の強さと腸管内圧のバランスが崩れることでできると考えられています。
憩室は無症状であることが多く、その時点では治療の必要はありませんが、便が詰まるなどして炎症が起こると憩室炎となり、症状がみられるようになります。憩室炎とは、消化管にできた憩室に炎症が起こる病気です。
憩室炎の症状の特徴
主な症状は左下腹部の痛み、圧痛、発熱などであり、ひどくなれば、周囲の臓器との癒着、瘻孔、膿瘍、腹膜炎といった合併症が生じることもあります。
憩室炎では、血液検査で白血球などの炎症反応に関連した数値の増加を認め、腹部CT画像検査では、炎症をきたしている憩室周囲の壁が肥厚する、あるいは周囲脂肪織が混濁するなど炎症所見が見られます。
炎症が非常に強く穿孔をきたしている場合は、本来では認められない空気成分が存在することもありますし、膿瘍形成を伴っている場合は、球状の膿の塊がCTなど精密画像検査で確認されます。
大半の大腸憩室は無症状で臨床上は問題になりませんが、しばしば憩室に炎症を起こして憩室炎を発症する、あるいは憩室から出血した際(憩室出血)には早急な治療が必要となります。
近年、大腸憩室炎や大腸憩室出血は増加傾向にあり、再発率も多く、特に憩室出血では1年以内に再度憩室出血を起こす確率が30%程度といわれています。
腹部大動脈瘤
腹部大動脈瘤は、大動脈が正常の太さの1.5倍以上に瘤状に膨らんだ状態を指します。
具体的には、大動脈の正常な太さが約2cmであるため、3cm以上に膨らんだ場合に「腹部大動脈瘤」と呼ばれ、この病状の原因は主に動脈硬化で、全体の90%以上を占めます。
腹部大動脈瘤の症状の特徴
腹部大動脈瘤はしばしば無症状で進行することがありますし、特に小さな瘤では何の症状も感じないことが一般的です。
サイズが大きな腹部大動脈瘤では、腹部が膨らんでいるように見えることがあります。この膨らみはしばしば触診で感じることもあります。
瘤が成長すると、腹痛が起こることがあり、痛みは腹部や側腹部に感じられ、時には背中や腰にも広がることがあります。
腹部大動脈瘤が大きくなると、腹部での脈動感が感じられることがありますし、食欲不振、消化不良、吐き気など消化器系の不定愁訴を引き起こすこともあります。
腹部大動脈瘤は、初期段階では自覚症状がほぼ現れないため、発見が難しい病気ですが、症状が現れるときには、すでに大動脈が破裂し、生命に危険が及ぶ段階に達していることが多いです。
破裂した場合、生存率は約20%と非常に低いとされていますが、破裂する前に発見し、適切なタイミングで手術を行えば、成功率は95%以上と非常に高くなるため、早期に腹部大動脈瘤を見つけることが重要です。
腹部大動脈瘤の原因
動脈硬化は、血管の壁が硬くなり、厚くなり、弾力性を失う状態を指していて、高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙などの生活習慣病が関与することが多いです。
その他の原因としては、感染症(梅毒、サルモネラ菌など)、炎症を引き起こす病気(高安動脈炎、ベーチェット病など)、ケガ、先天性の病気(マルファン症候群、エーラス・ダンロス症候群など)があります。
年齢とともに血管は劣化し、弾力性が失われる傾向があり、この変化により、大動脈の壁が弱くなり、拡張していく可能性があります。
腹部大動脈瘤の発生は50〜70歳がピークで、平均年齢は65歳前後であり、男女比は6~8:1程度と、男性に圧倒的に多い病気です。
また、喫煙は血管を収縮させ、血流を妨げることが知られていますし、血管の壁に損傷を与え、大動脈瘤の形成を促進する可能性があります。
高血圧は血管に負担をかけ、血管壁を弱めることがあります。これにより、大動脈瘤が発生するリスクが高まります。
腹部大動脈瘤は、遺伝が関与している可能性があり、家族がかかっている人がいる場合は、発症リスクが高まる可能性があります。
血管内の脂質やカルシウムが蓄積し、動脈壁に硬化斑を形成する動脈硬化症も、大動脈瘤の原因となる可能性がありますし、さまざまな要因が複合的に影響を与えることで、腹部大動脈瘤が形成されることがあります。
急性膵炎
横腹が痛いときに考えられる消化器の病気としては、「急性膵炎」が挙げられます。
男女ともに比較的中高年に多くみられる急性膵炎は、何らかの原因によって膵臓に炎症が起こってしまう病気です。
急性膵炎を引き起こす原因で最も多いのはアルコールの大量摂取であり、次に多いのは胆石症で、その他の原因は脂質異常症・薬剤性・外傷性・先天性などです。
急性膵炎は、女性より男性に多く発症し、その比は約2倍であり、発症年齢では女性70歳代・男性60歳代の方が多いことがわかっています。
急性膵炎では、「突然始まる激しい腹痛」が特徴で、重症化すると合併症を起こしてショック症状に陥ることもある病気です。
急性膵炎で最も多い症状は、非常に強い上腹部の痛みであり、膵臓は胃の裏側に位置しているため、背中の痛みを訴える方もいます。
その他の症状としては、多い順に嘔吐・発熱・食欲低下・腹部の張り・全身のだるさなどがあります。
病状が悪化すると、重症化して周囲の臓器へも炎症が進み、黄疸・意識障害・ショックなどを引き起こして、全身状態悪化の危険もありますので注意が必要です。
急性膵炎が起こった場合は、絶食して肝臓を休ませ、薬物療法で水分補充・炎症改善・消化酵素分泌抑制などを行います。
重症化すると、炎症は膵臓だけにとどまらずに肺・腎臓・肝臓などへも影響を及ぼす場合があるため、早めに適切な治療を行うことが大切です。
泌尿器の病気
横腹が痛いときに考えられる泌尿器の病気としては、「尿路結石症」が挙げられます。
一般的に、腎臓で濾過された尿は、尿管を通過し膀胱へ溜められ、尿道を通って排泄されることが知られており、この腎臓から膀胱、そして尿道の間にできる石を「尿路結石」と言います。
尿路結石の発症には食生活が大きく関係していると分かってきており、特に日本人の場合は、シュウ酸カルシウム結石症と呼ばれるものが圧倒的に多いです。
日々の生活における食事内容などでこのシュウ酸を摂りすぎることによって結石の主な原因に繋がるといわれています。
小さな結石が腎臓にできても無症状な場合がほとんどですが、尿路結石が腎臓から流れ出た途中で詰まってしまうと、わき腹から下腹部などの激しい痛みや血尿などの症状が出現することになります。
さらに、尿が下流の膀胱へと流れないために上流で尿が貯留して淀んでしまうため、腎盂腎炎などの尿路感染症を引き起こして腎臓の機能障害などが生じることになります。
筋肉や神経の異常
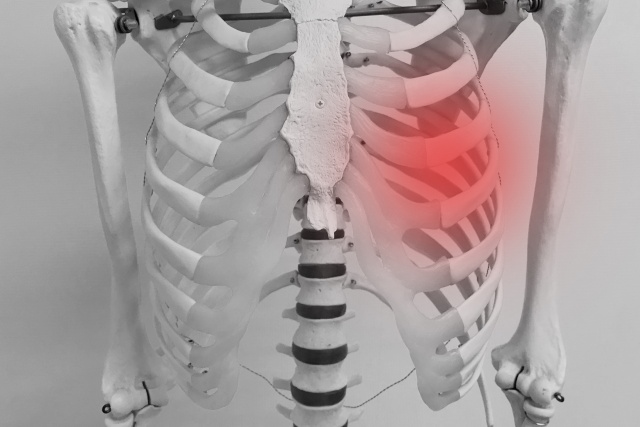
横腹が痛いときに考えられる筋肉や神経の異常としては、「肋間神経痛」が挙げられます。
脇腹や背中から胸にかけて、ビリッと電気が走るような痛みを肋間神経痛と言います。
肋間神経痛は、肋骨に沿って走っている肋間神経が痛む状態であり、主に脇腹、背中から胸にかけて電気が走るような鋭い痛みを呈するのが特徴のひとつです。
肋間神経は肋骨を引き上げたり、腹圧を加えたりするための指令を伝えるための神経であり、主に背中から胸腹部にかけて分布する末梢神経です。
肋骨の上部7対は、肋骨に沿って胸骨に向うように走行しており、下部5対は前下方に走行しており腹部に分布しているため、胸や背中、脇腹などに痛み症状を自覚します。
冬場など寒い時期になると起こりやすいのが特徴で、痛みがひどい際には内科など医療機関を受診することが大切です。
皮膚の病気
横腹が痛いときに考えられる皮膚の病気としては、「帯状疱疹」が挙げられます。
帯状疱疹は、水痘(すいとう)帯状疱疹ウイルスを原因として発症する病気です。
帯状疱疹の好発年齢は中高年齢層であると言われており、日常的に過大なストレスや加齢による水痘ウイルスに対する免疫力の低下を契機として、免疫機能の低下などに伴って体内に潜んでいたウイルスが再活性化することによって帯状疱疹を発症します。
帯状疱疹になると、発症の初めの段階では皮膚がぴりぴりするような痛みを自覚して、時間が経つと帯状に赤みや水疱形成などの典型的な皮膚症状が出現します。
帯状疱疹の発症には、加齢や疲労、ストレスなどによって免疫力が低下することと深く関係しています。
帯状疱疹にともなう神経合併症としては帯状疱疹後神経痛が多いと指摘されています。
まとめ
これまで、横腹が痛くなる理由、可能性のある病気や異常などを中心に解説してきました。
日常生活で食後や運動時に横腹が痛くなるメカニズムとしては、機能性ディスペプシアや慢性膵炎などの疾患が隠れていて食事の際に腹痛が生じる、あるいは運動する際に横隔膜の痙攣や酸素不足が引き起こされてお腹が痛くなるなどが考えられます。
また、横腹の痛みを呈する病気として、急性膵炎、尿路結石症、肋間神経痛、帯状疱疹などが考慮されます。
心配であれば、消化器内科や泌尿器科、一般総合内科や皮膚科など、それぞれの専門医療機関を受診して相談しましょう。
今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。