マダニから感染するライム病とは?ダニ媒介感染症の予防と対処法

ライム病という病気があります。ダニが媒介する病気で比較的珍しいのですが、時々発症する人がいます。ダニが媒介する病気には他にも様々なものがあります。ここではライム病をはじめとしてダニが媒介する病気を取り上げ、対処法について紹介します。
目次
マダニから感染するライム病

ライム病というのは細菌感染症の一種です。スピロヘータという種類の、ライム病ボレリアという細菌が感染することによって感染が成立します。ライムという名前は、アメリカのコネチカット州にある地名のことで、その土地でライム病ボレリアが発見されたことから名付けられました。
この細菌が人の体の中に入ってくるルートとしては、マダニに噛まれることによります。特に流行しているのがヨーロッパや北米で、屋外での生活でマダニに噛まれる機会が多いことから流行していると考えられます。アメリカでは年間3万人を超える人がライム病にかかっていると言われていますが、日本では時々見られる程度で、例えば北海道では年間10例弱の患者さんが報告されると言われています。
マダニは特に、動物の血を吸って成長しますから、動物が生息している場所に多く生息しています。具体的には野生のイノシシやシカなどがいる森の中などが中心となります。
ライム病の症状の特徴
ライム病は、感染した後1週間から3週間程度の潜伏期を過ごします。潜伏期が終わると、ダニが刺さっていた場所に小さな紅斑が生じます。この紅斑は数日で遠心性に広がり、中心部は反対に退色していきます。その結果、環状の病変となります。
この病変のことを、遊走性紅斑と呼び、ライム病の初期の症状として特徴的なものとなっています。この紅斑は感染した人の免疫反応によって起こってくるものです。免疫反応が落ち着くにつれて、数週間から数か月すると自然治癒していきます。
ライム病ボレリアが血液中に入り込むと、免疫応答の結果、熱が出たり、頭が痛くなったり、筋肉痛が出たり関節痛が出たりといった、風邪のような症状が出てきます。
多くの場合は、これだけで感染が終わり、症状は改善します。しかし、一部は数か月経過した後に、関節炎を起こしたり、脊髄神経根炎、心臓の伝道障害、顔面神経麻痺、無菌性髄膜炎などの様々な症状をきたすことがあります。さらには、最初に見られた遊走性紅斑が刺された部分とは無関係に多発します。
基本的にはこれらの症状は一過性のもので落ち着いてきます。しかし、しばしば再発し、変形を伴う慢性の関節炎や、進行性の脳脊髄炎、慢性萎縮性肢端皮膚炎などをきたすことがあります。
他にもあるダニ媒介感染症

ライム病以外にも、ダニによって媒介される感染症はいくつかあります。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は、最近になって日本で発見された病気です。ライム病は細菌が感染することによって引き起こされる病気でしたが、SFTSはダニが媒介するSFTSウイルスが感染することによって引き起こされる病気です。
おおよそ6日間から2週間程度の潜伏期間を経た後、発熱や消化器症状が出現します。消化器症状の中には、食欲低下や嘔吐、下痢などがあります。
ただそれだけでは終わらず、名前の通り血小板減少をきたすことが特徴です。血小板というのは、出血した時に血を止める成分ですから、血小板減少をきたすことによって重篤な出血を引き起こし、場合によっては命に関わることもあります。
国内では2013年に初めて患者が確認され、西日本を中心に毎年60人前後の患者が報告されている病気になります。
日本紅斑熱
日本紅斑熱は、紅斑熱群リケッチアという、細菌の一種による病気です。こちらもダニによって感染します。昔は年間多くても20人程度の感染者数だったのが、近年増加し、年間40人程度と倍近くに増加しました。西日本に多いのが特徴で、春から夏にかけて増加します。
潜伏期間は2日から8日ぐらいとやや短めです。発症すると、頭痛や発熱、倦怠感を感じます。刺した場所に発疹が見られるのも特徴です。
つつが虫病
ツツガムシというのは、田畑や山林、草むらなどに生息するダニの一種で、ツツガムシ病は、このツツガムシが媒介する病気です。日本紅斑熱に比べて、比較的多い発症率となっています。季節は日本紅斑熱とは異なり、10月から11月頃に集中しているのが特徴です。
潜伏期間は5日から14日くらいです。まずは高熱から見られるようになります。体をよく検索すると、ダニに刺された場所に、特徴的なダニの刺し傷が見られます。その後数日で、体に発疹が見られるようになります。
熱が出ている時を中心に、だるさや頭痛、リンパ節の腫れなどを伴います。
いずれも日本紅斑熱と特徴が似ていて、臨床症状だけからどちらかを判断するのは難しいです。
ダニ媒介感染症の予防と対処法
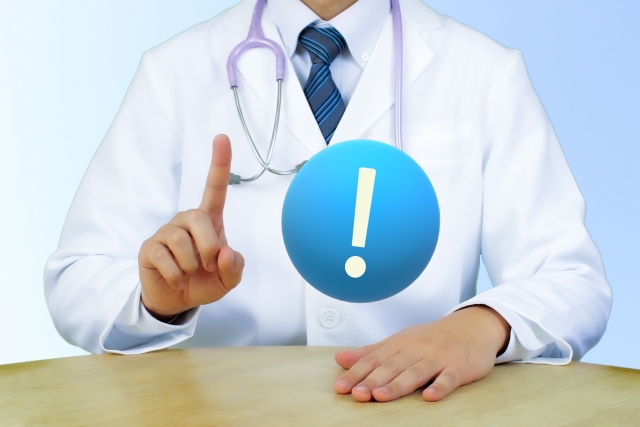
このようなダニ媒介感染症に感染しないための対策を確認しましょう。
ダニに咬まれないための予防
まずはダニに噛まれないことが大事です。特にマダニの活動が盛んな春から秋にかけては、噛まれる危険性が上昇しますから、草むらなどに入らないようのします。草むらの中でも、特に野生動物が生息している場所というのは感染の確率が上がりますから、動物が通った後のようないわゆる獣道は通らない方がいいでしょう。
しかし、そうは言っても、農作業や山菜採り、狩猟など山に入らなければならない機会は多くあります。そのような際には服装を気をつけるようにしましょう。
肌の露出をなるべく減らすことが大事です。長袖長ズボンを着用した上で、シャツの裾はズボンの中に入れて、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れるのが安全でしょう。足ももちろんサンダルなどは避け、しっかりと足を覆う靴を履いた方がいいです。帽子や手袋、首にタオルを巻くなどの対処もいいでしょう。
服の色も、できれば明るいものがいいです。マダニが付着した時に見つけやすいためです。
帰宅した後は、衣服の表面にマダニがついていないか確認してから部屋に入るといいです。もし、マダニがついていなかったとしてもすぐに洗濯したり、日光に当てて乾燥させたりするのが良いでしょう。というのは、マダニは成虫になると大きく目視しやすいのですが、成長過程では非常に小さく、見えないことも多いからです。
ダニに咬まれたときの対処法
ダニに噛まれてしまうと、すぐにダニを引き剥がしてしまいたくなりますが、それはあまり良くありません。ダニは動物や人の体に乗り移ると、まず血を吸うのに適した場所を探して体の上を歩き回り、場所が決まると口先をさして吸血を始めます。
この時に、血を吸うだけではなく、セメント質を分泌して口の周りをしっかりと固めます。1日もすると、口の周りはがっちりと固められますから、ダニの体を引っ張っても取れなくなってしまいます。このまま1週間や10日間ずっと血を吸い続けるのです。
このように、口先が皮膚の中に固定されますから、無理やり引っ張るとマダニの体がちぎれて口元だけが皮膚に残ってしまいます。これを放置すると、アレルギー反応が起こったり、感染症がひどくなったりすることがありますので、すぐに取り除かなければなりません。
しかし取り除こうにも、口先だけを取り除くのは非常に難しくなるため、その部分の皮膚全体を切り取るような軽い手術を行わなければならないことも珍しくありません。
そのため、ダニに噛まれた時には、そのまま病院を受診するようにしてください。病院では、ピンセットや専門の器具を使うことによって、口の部分を残さずにダニを外すことができます。





