寝起きに喉が痛い!乾燥や口呼吸などの原因と痛みを改善する方法

朝起きたときに喉が痛くなっていると、風邪の始まりではないかと不安になる方も多いことでしょう。そして、時間が経つとすっと痛みが引いていくことも少なくありません。こうした喉の痛みはどのような原因で起こってくるのでしょうか。
目次
寝起きに喉が痛くなる原因

寝起きに喉が痛くなる原因としては次のようなものが挙げられます。
風邪の初期症状
まず不安になるのが風邪の初期症状でしょう。風邪は日中に症状が出てくることもありますが、圧倒的に寝ているときに起こってくることが多いものです。
寝ているときは、後述するように喉が乾燥し、細菌やウイルスが繁殖しやすい環境が整っている状態と言えます。水気を帯びた喉の粘膜であれば、白血球を始めとした免疫細胞が喉の粘膜表面までやってきやすいので、多少の細菌やウイルスがやってきてもすぐに退治することができます。
一方で、喉が乾燥してしまうと免疫細胞はなかなかその場所にたどり着けなかったり、たどり着いたとしても十分に効果を発揮することができなかったりして、細菌やウイルスの増殖をとめられないことがあります。その結果として、風邪を引いてしまうことがあるのです。
また、寝ている間は増殖した細胞に対する体全体の免疫反応が活発化する時期でもあります。すなわち、微生物が喉で増えた上に、その微生物に対抗するための免疫が強く体の中で反応する結果、熱が出たり、咳や痰が出たりと言った体の防衛反応全体が活性化させられるのです。
それらの全身反応に加えて、喉では微生物に対する免疫反応が活性化されます。乾燥していて十分に活動できなかった免疫細胞も、微生物があまりに増えてくると対抗するために喉の浸潤環境を整え、炎症反応を起こします。
この炎症反応は、喉の腫れに加えて喉の痛みを来します。炎症が起こっている組織の特徴としては、何もしなくても痛い、触ると痛い、といったものがあります。そのため、喉で炎症が起こるとつばを飲み込んだり、表面から喉を触ったりしただけでも痛みを感じるようになるのです。
喉の乾燥
喉が乾燥していると、微生物が感染していなくても痛みが起こってきます。
喉は粘膜によって表面をカバーされています。この粘膜は、全体を湿潤した環境に整えることで気道に入ってくる空気を加湿する効果があるほか、前述のように免疫細胞を活動しやすくする効果を発揮します。また、ものを飲み込むときにスムーズに飲み込めるようにしたり、唾液によって自分自身の組織が消化されるのを防いだりする効果もあります。
しかし、粘膜というのは湿潤した環境を整える働きを持っている一方で、乾燥してしまうとその効果を発揮できない組織でもあります。乾いてしまうと湿潤させるための水分を分泌する機能も低下してしまい、湿潤環境を保てなくなってしまいます。
そのため、喉が一定以上乾燥してしまうと粘膜自体が損傷を受けて傷ついてしまいます。この損傷によって喉に痛みを感じます。損傷した粘膜に物質が触れると、痛みを感じますからものを飲み込んだときはもちろん、空気を吸うだけでも痛みを感じてしまうこともあるのです。また、ちりやホコリを吸い込んでしまうと痛んだ粘膜にそれらの微細な物質が付着して痛みを感じてしまいます。
アレルギー
アレルギー反応によっても喉の痛みが出てくることがあります。
微生物による感染症の場合には免疫細胞が集簇(しゅうぞく)して炎症反応が起こり、喉が痛くなるのでした。
アレルギー反応は、元々体に対して悪影響を及ぼさないような花粉やホコリなどの微細な物質に対して、免疫細胞が異常に反応してしまい炎症が起こることを言います。そのため、微生物による炎症と同じように喉で炎症が起き、喉の痛みが起こってきます。
アレルギーによる反応である場合には、多くの場合咳やくしゃみ、鼻水を伴います。これらも異物に対する免疫細胞の反応によるものです。
また、後ほど取り上げるようにアレルギー性鼻炎は口呼吸の原因にもあります。
寝ている間に喉が乾燥する原因
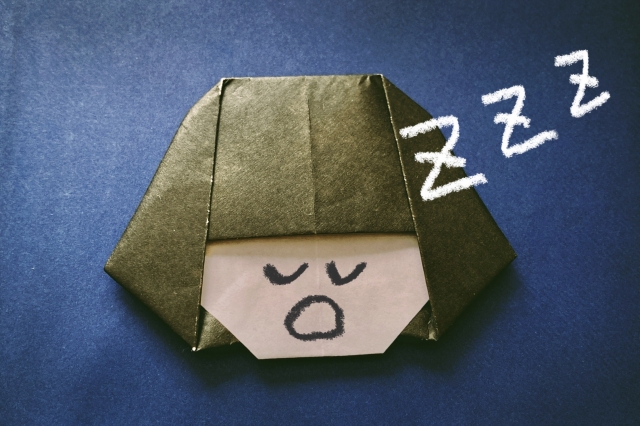
乾燥が喉の痛みと密接に関わっていることを見てきました。では、どのような場合に喉が乾燥してしまうのでしょうか。
いびき・口呼吸
日常的に口呼吸をしている場合、喉は乾燥しやすくなります。
もともと気道は全体に湿潤した環境になっています。これは、湿潤環境でないと粘膜が損傷してしまったり、微生物が増殖してしまったりするため、鼻から喉、気管、肺に至るまで湿潤な空気が通るように工夫されています。
そのための工夫として、気道は粘膜で覆われている他、鼻で加湿される事で外気が乾燥していても安定して湿った空気が気道に入ってくるようになっています。鼻の中は非常に複雑に風が通るようになっていて、その通り道全てが粘膜で覆われていて、空気が加湿されるようになっています。
一方で、口の中はあまり複雑ではない空気の通り道となっています。外気がそのまま喉に入っていく構造になっていますから、口呼吸であればほとんど加湿されない空気が喉、気管へと入っていってしまいます。そのため、鼻呼吸に比べて口呼吸の方が圧倒的に喉が乾燥しやすいのです。
寝ているときに単純に口呼吸をしている場合も問題になりますが、いびきをかいている場合はほとんどの場合口呼吸になっているため注意が必要です。鼻呼吸でいびきをかくことも時折ありますが、ほとんどは口呼吸ですので、いびきをかいているとなればまず口呼吸と考えていいでしょう。
すなわち、いびきをかいているときは喉の乾燥を来している場合がほとんどですから、注意が必要なのです。
口呼吸になる原因はいくつも考えられます。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に無呼吸状態になる病気です。無呼吸というのは、医学的には10秒以上呼吸が止まっていることを言います。一晩の睡眠中に30回以上も呼吸が認められる場合や、1時間のうちに5回以上の呼吸が認められた場合に睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
睡眠時無呼吸症候群であることは、なかなか自分自身で気づくことは稀です。寝ている時のことですから、気づかないことがほとんどなのです。多くの場合家族の人に指摘されて気づくか、睡眠の質が低下していることによって日中の眠気が強くなり、日中の眠気の原因を調べる中で睡眠時無呼吸症候群であることがわかることが多いです。しかし、それらの理由なく、なかなか診断に至らないことも多く、潜在的な患者数は日本全体で300万人とも言われています。
睡眠時無呼吸症候群を放置すると、高血圧が進行したり、心臓や脳血管障害が起こる確率が増加すると言われています。
睡眠時無呼吸症候群の場合、口呼吸をしていることが非常に多くあります。口呼吸のせいで睡眠時無呼吸症候群になっている場合も多いのですが、睡眠時無呼吸症候群が原因で、口呼吸になっていることも時々あります。睡眠時無呼吸症候群では呼吸の量が低下し、無呼吸の後に大きな呼吸となることがほとんどです。この時に、鼻では十分呼吸できないことから、口呼吸になるのです。
合併症が起こる可能性もありますので、しっかりと治療する必要があります。
慢性副鼻腔炎
口呼吸の原因の多くは、鼻が詰まっていることによって仕方なく口で呼吸することによります。慢性副鼻腔炎の場合、鼻の奥の方の副鼻腔が炎症を起こして粘膜が肥厚してくることにより、空気の流れが阻害されてしまいます。そのため、鼻で十分呼吸することができず、口呼吸になってしまいます。
軽度であれば内服治療で治療が行われますが、重度になってきている場合には手術も検討されます。
花粉症・アレルギー性鼻炎
花粉症の場合も、アレルギー性鼻炎の場合も、鼻の通りが悪くなります。鼻水が出ることによって空気の流れが阻害されることもありますし、鼻粘膜が炎症によって肥厚してきて鼻呼吸が難しくなり、口呼吸となってしまうことがあります。
対処法としては、抗アレルギー薬の内服や点鼻が行われます。これらによって、鼻水の量が減少し、鼻粘膜の肥厚が改善することによって、鼻呼吸が楽になる場合が多いです。
骨格や歯並びの影響
元々の骨格や、歯並びが悪いことによって口呼吸になることもあります。鼻中隔湾曲症によって鼻の通りが悪くなる、あるいは、口元の骨格や歯並びが悪いことによって口を閉じるのが困難になると口呼吸につながります。
歯並びの影響としては、いわゆる出っ歯の影響が口呼吸の原因としてはよく見られます。上の前歯が極端に前に出ることによって、常に口が開いた状態になってしまうのです。
エアコン
喉に入ってくる空気が加湿されなければ喉が乾燥してしまいますが、元々の空気が乾燥しているとそれだけ喉に入ってくる空気は乾燥の度合いを増してきます。
日常生活でより乾燥した空気を作り出しているのがエアコンです。冷房であっても、暖房であっても、エアコンから出てくる空気は乾燥した空気になります。そのため、エアコンをつけた部屋で寝ていると口呼吸であればもちろん、鼻呼吸であっても加湿が十分なされずに喉まで空気が届き、喉の乾燥を来してしまう場合があるのです。
エアコンの風を直接吸い込まないということが大事です。また喉の渇きがひどいときには乾燥の度合いによっては加湿器を使うことも必要です。
水分不足・脱水
寝る前に、就寝中トイレに行かずに済むようにと水分をなるべく取らないようにしている場合も、夜間の脱水によって喉の乾燥を来すことがあります。
人間は、寝ている間にもかなりの量の汗をかきます。服にしみこんで触れる程の汗ではなくても、肌の湿度を保ったり、喉の乾燥を防ぐために多くの量の水分が蒸発していきます。その量は季節を問わずおおむね200~400ml程度と言われています。もちろん、暑くて汗をかくような状況であればさらに増加します。
これだけ水分が体内から喪失してしまうと、粘膜の湿り気を維持するために分泌する水分が不足してしまい、粘膜が乾燥してしまいます。そのため、脱水によって寝起きに喉が乾燥して痛みを感じる事があるのです。
寝起きの喉の痛みを改善する方法

では、寝起きに喉が痛くならないようにするためにはどのような方策が良いのでしょうか。
喉を乾燥させない
喉を乾燥させないためには、前述のような喉を乾燥させるような条件をなるべく避けるのが重要です。
脱水にならないように寝る前にコップいっぱいでもいいので水分を取るのは効果的です。また、いびきがあって口呼吸をしている場合は、枕があっていなくていびきをかいている場合もありますので、寝具の調整が効果的な場合もあります。
エアコンを使用している場合は、なるべく弱めの設定とし、エアコンの風を直接吸うことがないようにしましょう。特に冬期は加湿器を併用して湿度が下がらないように調節しましょう。
特に喉の痛みが気になるときは、マスクをつけて寝るというのも効果的です。呼気には水分が多く含まれていますから、マスクが湿気を捉え、吸気を加湿してくれます。毎日のように朝起きると喉が痛い場合には試してみるといいでしょう。
市販薬・市販のグッズを活用する
乾燥を防いでもなお喉が痛い場合は、喉の炎症を抑える薬を使用するのも一手です。トラネキサム酸は粘膜の損傷部位の修復に役立つため、トラネキサム酸を配合した喉の痛みに対する薬を使用すると良いでしょう。
また、最近ではいびき対策グッズが多数販売されています。それらのグッズを使用してなるべく鼻呼吸にすることで喉の痛みを抑えることができます。
ただ、基本的には乾燥を防ぐ対策をした上でもなお喉の痛みがある場合の対症療法だと考えましょう。乾燥していることそれ自体が感染症の原因になる場合もあります。乾燥しないための対策を第一に考えましょう。





