
アルコールで腹痛や下痢が起こるメカニズムと急性膵炎・慢性膵炎
アルコールと腹痛の関係、急性膵炎・慢性膵炎の特徴を解説。アルコールの摂取が引き金となり、胃粘膜に障害を与えることで腹痛が発生します。急性膵炎はアルコールや胆石症が原因で、主な症状は激しい上腹部痛です。慢性膵炎は飲酒により膵臓機能が低下し様々な症状が出現します。予防には節度ある飲酒やバランスの取れた食事が必要です。

アルコールと腹痛の関係、急性膵炎・慢性膵炎の特徴を解説。アルコールの摂取が引き金となり、胃粘膜に障害を与えることで腹痛が発生します。急性膵炎はアルコールや胆石症が原因で、主な症状は激しい上腹部痛です。慢性膵炎は飲酒により膵臓機能が低下し様々な症状が出現します。予防には節度ある飲酒やバランスの取れた食事が必要です。
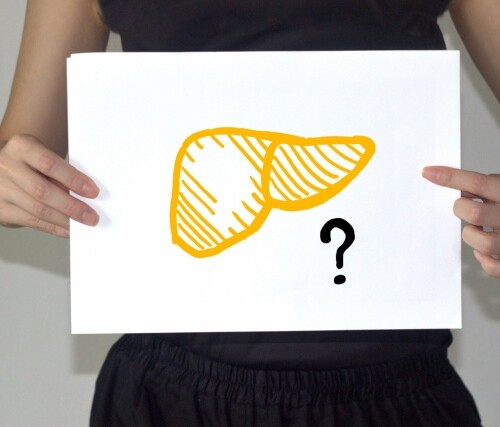
肝性脳症は肝機能低下により有害物質が脳に影響を及ぼし、意識障害や精神症状を引き起こします。予防や治療には食事療法、薬物療法、外科的治療があり、早期発見が重要です。

お腹が鳴る原因は腸内ガスや蠕動運動によるもの。多くは心配不要ですが、生活習慣改善が効果的。症状が続く場合は受診を。

脾臓の痛みの原因は脾腫や損傷、腫瘍などが考えられます。特に脾腫は感染症や血液疾患などの基礎疾患による合併が多く、左上腹部の痛みや早期満腹感を引き起こす場合があります。診断には画像検査や血液検査が必要で、治療は原因疾患への対応が基本ですが、重症例では脾臓摘出が検討されることもあります。

便秘が原因で起こる虚血性腸炎について、症状、重症度の違い(軽症の一過性型から重症の壊疽型まで)、検査・治療法、生活習慣改善による予防策を詳しく解説しています。

少量の便が何回も出る「頻回便」は、便秘や大腸ポリープ、過敏性腸症候群、大腸がんなどの前兆となることがあります。この記事では、その原因や対処法、治療法について解説しています。

呑気症はストレスが原因で空気を飲み込み、ゲップやおならが増える症状。予防には、ゆっくり食事し、ストレスを減らし、噛みしめ癖を治すことが重要です。
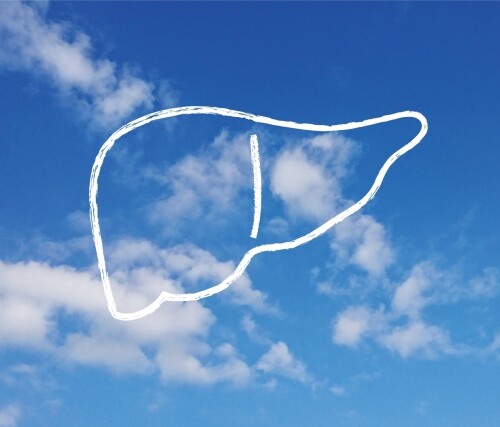
肝硬変は肝炎などが原因で進行する病気で、代償期では症状が軽微ですが、非代償期では黄疸や腹水など重篤な症状が現れます。予防や早期治療が重要です。

大腸ポリープは40歳以降に多発し、特に腺腫性ポリープはがん化リスクが高いとされています。本記事では、がん化しやすいポリープの特徴や検査方法、病理検査の重要性を解説します。

胆のう壁肥厚は胆のう炎や腺筋腫症が主な原因で、精密検査や治療が必要です。胆石予防や適切な生活習慣が重要とされています。